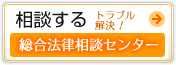倒木被害と工作物責任について
先日の台風21号、24号により被害を受けられた皆様に謹んでお見舞い申し上げます。
■ 大阪では、特に21号の際に各地で倒木被害が発生し、高槻市北部の樫田地区(山間部)では100ヘクタール以上、1万数千本以上の被害が発生しているとの報道にも接しました。その他、未だに被害の全容が明らかではない地域があるようです。
今回の倒木被害は、もちろん、台風の勢力それ自体が大きかったということが一因かと思われますが、今後、樹木自体の状態が影響して、台風時、大雨時などに、大規模な倒木被害が発生する可能性があります。
というのも、、、
■ ご存知の方も多いかと思いますが、第二次世界大戦中の必要物資や戦後の復興資材を確保するために大量の木材が必要とされたことから、かつて我が国では大規模な森林伐採が行われ、これにより国土の多くの部分がはげ山になっていました。
医療事故調査制度
初めまして,中村克宏と申します。
私は,弁護士会の人権擁護委員会の医療部会に所属しており,医療にまつわる人権問題の研究をしたり,研究結果の報告をしたりしています。そして,医療部会で現在取り上げているテーマが「医療事故調査制度」です。
医療事故調査制度は,平成27年10月に施行された比較的新しい制度です。医療機関は,医療によって予期せぬ死亡・死産が生じたと判断した場合,事故を医療事故調査支援センターに報告するとともに,院内で調査委員会などを立ち上げ,原因究明・再発防止策の検討等を行い,調査結果を遺族と医療事故調査支援センターに報告することとされています。そして,遺族は,院内調査結果に納得ができない場合は,医療事故調査支援センター(第三者機関)に調査を依頼することができます。
このように,医療事故調査制度は,事故の原因を究明するとともに,事故情報を医療事故調査支援センターにて集約し,分析をして,今後の再発防止に役立てることを目的としています(責任追及を目的とした制度ではありません)。
セクシャルハラスメントは何故起きるか
弁護士の仕事の一つに会社内で存在が指摘されたセクシャルハラスメントやパワーハラスメントについて、会社の依頼を受けて調査・報告をするという仕事があります。
当事者および関係者のヒアリング等を行って事実を特定し、法的に評価していくのですが、女性が被害者となっているセクシャルハラスメントの案件においては女性弁護士の出番が多くなりがちです。
最近、セクシャルハラスメントの加害者の男性にヒアリングを行ったのですが、その中で、「彼女から明確に嫌だと言われたことがなかったので喜んでいると思っていた。」という趣旨の発言がありました。
人の感情には、とても嫌>どちらかというと嫌>どちらでもない>どちらかというと嬉しい>嬉しい、というグラデーションがあると思うのですが、拒否されていない=喜んでいると処理する認知の歪みに思わず言葉を失ってしまいました。
こういう話をすると、「嫌と言わない方が悪いんだ。」という人がたまにいらっしゃいますが、そうではないと思っています。
ちいきほうかつでのごそうだん
昨年12月20日以来のブログ当番です。
大阪弁護士会高齢者障害者総合支援センター「ひまわり」では、地域包括支援センター等の相談員さんの相談に乗っています、と、12月20日のブログで書きました。
私も、地域包括支援センターで、相談に受けたり、電話相談で相談員さんの相談を受けたりしています。
地域包括支援センターからのご相談で、最近、立て続けに、親子で、自宅で生活しておられたが、双方とも高齢、病気などで、それまでできていた金銭の管理ができなくなった方のご相談に乗っています。もちろん、独居や高齢のご夫婦でも同様の問題が生じています。
誰かがお手伝いしなければ、買い物もいけませんし、病院代も支払えません。たくさんやってくる郵便物もたまってきます。
そして、そもそも通帳などが不明で、財産のありかがわからないことにもよく直面します。
成年後見制度の利用や、財産管理契約の締結によって、弁護士が、財産や収支を管理したりご本人にとって適切な住まいを一緒に検討したりして、解決を図ることが多いです。
地域で、困っておられる世帯の方がおられたら、地域包括支援センターに相談してください!
国選弁護について思うこと
先月、弁護士になって初めて無罪判決を獲得しました。
ここだけ見るとよかったじゃないか!となるのですが、弁護人としては非常に不本意で、公訴事実3件全ての無罪を争っていた中、無罪になったのは1件だけ、2件については有罪とされ、しかも、実刑判決となってしまいました。
保釈中の被告人に実刑判決が下された場合、保釈はその効力を失いますので(刑訴法343条)、被告人は判決を受けたのち、バーの外に出ることなく、法定脇の小さな扉から拘置所に連れて行かれることになります。
荷物を取りに戻るなどそんな悠長なことはできませんので、保釈中の被告人で実刑が予測される場合には、事前に荷物をまとめてくるよう言うようにします。
このようにして被告人が再び勾留をされるに至ってしまった場合でなおかつ控訴する場合、身体拘束から解放されるためには再び保釈をする必要があるのですが、1審判決が出てから控訴審の国選弁護人が選任されるまでには1か月ほど時間が空いてしまうのです…!
これ、かわいそうじゃないですか?