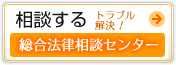MBSラジオ「弁護士の放課後 ほな行こか(^o^)丿0126」 今夜放送
テーブルの向こう側
昨秋、2人目の子どもを授かりました。
家族と事務所と、より多くのものを背負うプレッシャーは一入ですが、詰まるところそれが自分を強く突き動かしてくれているように感じます。
さてさて、現実は厳しく、通帳を見ても財布を見ても不景気なことこの上なく、受け取るものといえば請求書、増えるものといえば加除式図書くらいしかありませんが、家族が増えたり、上の子の進学なども近づけば、これも妖怪の仕業なのか、どうしても引っ越しや新居の購入などの夢にもとりつかれます。
そんなこんながありまして、先日、新築マンションのモデルルームというものを思いつきでいくつか見て回りました。
複数のモデルルームを訪問されたご経験のある方はおわかりでしょうが、どこであってもおよそ同じような流れでことが進みます。
2/7 いじめシンポのご案内
1/14に小島先生が,1/16に山口先生が,
既にブログ記事で触れておられますが,
私も,このシンポジウムの事務局の一人として,
「いじめ新法で何が変わるか」
~増える「いじめ」相談に弁護士としてどう対応する?~
のシンポの紹介をしたいと思います。
このシンポのもともとの出発点は,次のようなものでした。
いじめによる重大事態が起こった場合に,
第三者調査機関が立ちあげられ,
その委員の構成員に弁護士が就任することが多くなりました。
そこで,大阪弁護士会子どもの権利委員会の
学校部会のメンバーが中心となり,
・第三者委員の公正な人選はどうあるべきか
・調査機関はどこに付属するか,常設か,臨時のものか
・調査方法で工夫すべき点,留意すべき点にはどのようなものがあるか
・「事実認定」の方法,「説明」の方法
2/7 シンポジウム「ストップ!悪質商法・迷惑勧誘」
大阪弁護士会広報室の小島です。
2月7日、日弁連主催のシンポジウム「消費者法の課題と展望Ⅸ ストップ!悪質商法・迷惑勧誘~Do-Not-Call/Knock制度の可能性~」を、大阪弁護士会館にてテレビ中継します。
◆消費者の要請なしに行われる取引の勧誘(不招請勧誘)は、それ自体が迷惑であるだけでなく、悪質商法の温床ともなりやすいものです。
電話勧誘や訪問勧誘という方法の場合、消費者が応答を強いられるため、その傾向がより顕著なものとなります。
◆望まない電話勧誘を未然に防ぐための仕組みとしては、Do-Not-Call制度(電話勧誘拒否登録制度)があります。この制度は、2003年に全米で導入され、世界的広がりをみせ、2014年には韓国とシンガポールでも運用が始まっています。
他方、訪問勧誘では、アメリカの地方自治体やオーストラリアなどでは、訪問販売お断りステッカーに法的な効果が認められています(Do-Not-Knock制度)。
◆本シンポジウムでは、不招請勧誘の規制のあり方としてのDo-Not-Call/Knock制度の可能性を検討していきたいと思います。
大阪弁護士会広報室の小島です。
大阪弁護士会では、2月7日、シンポジウム「MBSアナウンサー 西 靖さんと考える取調べのこと,可視化のこと~可視化が法律になるって,ホント?~」を開催します。
①なぜ今、取調べの可視化が法制化されるのか、
②いつどのような法律になるのか、
③法制化されることにより何が変わるのか、
という可視化に関する素朴な疑問をMBSの西 靖アナウンサーと一緒に考えようと思います。
日時 : 2015年2月7日(土) 午後1時~午後4時
場所 : 大阪弁護士会館
詳しくは大阪弁護士会HPをご覧ください。