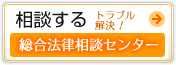事例と対話で学ぶ「いじめ」の法的対応
今年1月11日のブログで「書籍が出版されます」と宣伝しましたが、この3月、無事に出版されました。
執筆・編集期間約2年。
タイトルは、
「事例と対話で学ぶ『いじめ』の法的対応」(エイデル研究所 発行)です。
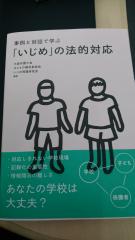
子どもの権利委員会の中でも、いじめ調査の第三者委員会やいじめの対応に興味のある弁護士が有志として「いじめ問題研究会」を作って集まり、執筆したものです。
せっかくですので、内容をご紹介させて頂きます。
本書は、平成25年6月に成立した「いじめ防止対策推進法」と、
同法に基づく「いじめ」へのあるべき対応を、法的に解説するものです。
1つめの特徴は「逐条解説ではない」です。
重要と思われる条文を取り上げ、基本的な解説を行っています。
ちょっと待って
弁護士の西塚直之です。
弁護士業務の1つとして、市役所や区役所で法律相談をお受けすることがあります。
「先生、今日は全ての枠が埋まってます。」と言われることがたいていで、
それだけみなさん悩みを抱えておられるんだなぁと思います。
相談の中には法律相談ではなく人生相談で終わることもありますが、
とにかく来たときよりも気分よく帰っていただければ、
充実感もひとしおです。
法律相談は、離婚、相続、不動産、労働といろんな話があります。
その中でも私が気になっているのが「債権回収会社から・・・」という相談です。
正当な請求も勿論あります。
しかし、なかには消滅時効を援用すれば支払いを免れることができるのに、
「1万円でもいいから払ってくださいと言われたんですが・・・」とか
「訴えられてしまいました」と
相談に来られる方がいらっしゃいます。
憲法、知ってますか?
こんにちは。室谷光一郎です。
最近は「リーガルハイ」「グッドパートナー」等のドラマの話ばかりを書いておりましたが、今回は憲法のことを書いてみたいと思います。
昨年から憲法が熱いように感じます。
そして、昨年の国会の中で、安倍首相が「芦部信喜」なる人物を知らなかったことがちょっとした話題になりました。
皆さん、「芦部信喜」なる人物をご存知でしょうか。
弁護士を含む法律家の皆さんなら、おなじみの司法試験の際の憲法「必読書」を記した芦部信喜東京大学名誉教授のことです。
この憲法必読書は「芦部憲法」とも呼ばれ、法律家の共通言語のひとつとも言えます。
が、芦部信喜先生のことや芦部憲法を知らなかったとして何か問題になるのでしょうか?
そもそも、法学部以外の方、法律家の方以外の方には、芦部信喜先生、芦部憲法の認知度が高いように思われません。それ自体は特に大したことではありません。
相続放棄と固定資産税
被相続人が多額の債務を残して亡くなった場合、相続人としては相続放棄の手続を執ることが考えられます。通常、相続放棄を行った場合、「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。」(民法939条)とされており、債務を支払う義務はさかのぼってなかったことになります。
しかし、固定資産税については、少し注意が必要です。
地方税法343条は、次のように規定しています。
1項:固定資産税は、固定資産の所有者・・・に課する。
2項:前項の所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者・・・として登記又は登録されている者をいう。(略)
すなわち、被相続人の死後、相続放棄までに相続登記がされ、課税処分がされてしまうと、相続放棄と課税処分のどちらが優先するのか?という問題が出てきてしまうのです。
これについて、横浜地判平成12年2月21日(判例自治205号19頁)は、代位による相続登記により登記簿上所有者とされている者に対してなされた固定資産税の賦課処分は、その後登記名義人が相続放棄をしても適法である、と判示しました。
相続法制改正の話
はじめまして。弁護士の中森亘です。
酷暑が続くなか、涼しいお話をお届けしたいところですが、司法制度や法令改正等を取り扱う司法委員会から選出されている関係で、今回は法令改正のお話をさせていただきます。
さて、現在、民事系では、民事執行手続や相続法制、公益信託制度等の改正作業が進んでいます。中でも相続法制は皆さんに身近な問題かと思います。既に法制審議会から中間試案が公表され、9月末を期限にパブリックコメントに付されています。
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900291.html
ポイントは5つあり、①配偶者の居住権を保護するための方策、②遺産分割に関する見直し、③遺言制度に関する見直し、④遺留分制度に関する見直し、⑤相続人以外の者の貢献を考慮するための方策、です。