弁護士会から
広報誌
オピニオンスライス 2月号
-
信州大学特任教授・法学博士
山口真由さん
YAMAGUCHI, Mayu
東大総代、大学3年次に司法試験合格、財務官僚と華々しいキャリアで、現在は、コメンテーターや講演でも活躍されている山口真由先生。山口先生は、実は、比較法的家族法の専門家。これからの家族法制・家族観について教えていただくとともに、一見すると窺えないこれまでの様々なご苦労も伺いました。山口先生の「優しさ」が伝わる素敵なインタビューでした。
-

これまでのキャリア~財務官僚として~
東大法学部の3年次に司法試験に合格されて、その後は財務省に入省されたとのことですが、先に官僚になられたのはなぜだったのですか。
もともと官僚に憧れがあったのと、その当時は、後から官庁に入るという道がまだなかったように思ったからです。
司法試験に受かるとも思っていなかったので、受かった後は結構迷ったのですけれども、面接に行った事務所の先生から、雅子様の婚約を見た小学生のときからやってみたいと思っていたんだったら、1回やったほうがいいんじゃないのと言われて、財務省に行きました。
その後、官僚として生きる中で、一番大変だったことはどんなことでしたか。
私はすごい勉強ができて、自分はエリートの中のエリートだと思って財務省に入ったので、自分が全然仕事ができないポンコツだということを認めることができなかった。
認めることができたら、先輩とかに今自分が困っているという状況を伝えられたと思うし、そこで助けを求められたと思うのですけれども、そういうことが全くできないまま辞めたんです。そこは今でも、もう少し続ける道があったんじゃないかとか、自分自身の弱さをもっと正直に出したほうがよかったんじゃないかと思っています。
今振り返られて、具体的にどういうところが足りなかったとお考えなのですか。
私は、読み書き、特に読むのは得意なんだけど、脳の構造というか、ワーキングメモリーがすごく小さいみたいなんです。
仕事というのは全部マルチタスクですよね。特に年次が下のときはそうで、何かを読んでいるときでも上の人に来ている電話はちゃんと聞いて、何が行われているのかをそれなりに理解していなければいけない。
財務省は特にそれが強く求められたんです。自分がメールを読んでいるときに、上司の席に来ている電話を聞いてなくてはいけなくて、その電話が終わったすぐ後に「あれ出して。」と言われて、その「あれ」が上司とずれないようにしなければいけない、みたいなロジスティクスがかなり重要な要素を占めているんです。
しかし、私はそういう気働きが一切できなかった。何かを見ているときに物を聞くということが、私の小さなワーキングメモリーが徹底的に拒否したので、本当に仕事ができなかったです。
それは組織で働くということの難しさなのでしょうか。
今振り返ると、色々とやりようはあったと思いますけれども、私は組織で働くのは本質的に向いているタイプじゃないと思いますし、それも分からなかった。エリートの王道に行くんだと思って財務省に入ったのに、仕事ができない。当時は自信のなさゆえに自分の成績を拠り所にしてきたところもあり、それにもかかわらず、自分よりも公務員試験の順位が下の人たちのほうがずっと自分より仕事ができて、私はその人たちに気遣われて助けられて仕事をしているということを認めることができなかったし、「ありがとう。」と言えなかったし、自分が今困った状態にあるということもうまく伝えられなかったと思います。

これまでのキャリア~弁護士として~
その後、弁護士になられて長島・大野・常松法律事務所に入所されたのですね。
はい。1年目はもう水を得た魚でした。1~2年目は手足だから、ひたすらリサーチをやるんですが、リサーチは学校の勉強とほとんど同じだったので、リサーチなら任せて、と。パートナーにリサーチ結果を出して「全ての記録を読みましたが同じ事例はありませんでした。」と報告して「これをこの時間で読んだのか。」と驚かれるんです。私は読む速さだけは光のように速いと言われるので、リサーチの神みたいな感じでどんどんリサーチを受けていました。
5年間弁護士をされて、留学に行かれたと伺いました。
留学の前に弁護士は辞めているんです。年次が上がってくるにつれて、自分で考えて判断してほしいということを言われるようになったんです。前例は分かった、でも法律的な解釈は幅があるのだから、どういう道があるんだ、と。私、勉強でその部分を考えたことがなかったんです。
自分の上にはすごく賢いパートナーがいるわけで、下手の考え休むに似たりだと思って、私が何か解決方法を考えて仕事を止めるよりは、後輩から上がってきた資料を自分で見もせずにそのままパートナーにばんと送って、パートナーに赤字で直されたのを、そのまま修正を全て反映して依頼者にご送付していたんです。
そうすると、やはり伸び悩んで、1年に1回の評価面談があるんですけれども、あるときから芳しくない評価を受けるようになったんです。そこからがすごくつらかったです。私は大学を卒業するときに、自分は選ばれた1人で、このまま王道中の王道を行くんだ、全ての女性初を塗り替えていくんだという期待を周囲からも受けたし、自分も当然そうだと思っていたんです。なのに、そのときが人生のピークで、22歳からだだ下がりな人生、ここから80歳まで生きなきゃいけないのか、どうしよう、みたいな感じでした。
弁護士としてご苦労されたことはどういうことですか。
自分がどうして評価されないのかを理解することが難しかったですし、そこでもやっぱり助けてほしいと言えなかったことです。
弁護士になった当時、大手の渉外事務所の弁護士には4つのタイプがあると聞きました。1つ目はM&Aやコーポレート案件をやるスーパーコーポレートローヤー。2つ目はかつての独禁法や環境法のような小さな分野を耕して大きくしていくニッチプレーヤー。3つ目は税法の弁護士とか、クライアントの前に必ずしも出ないけれども弁護士が相談をしに行くローヤーズローヤー。4つ目は予防法務の分野においても重要な訴訟担当弁護士のリティゲーター。
そのとき、私は、「エリートの王道は“スーパー”がついているスーパーコーポレートローヤーだ!」と思って、M&Aの担当を希望したんです。しかし、取引というのは多方面への目配りが必要で…ここではこういうことが起こっていて、ここではこんな問題があって、という状況で常に判断をしていかなきゃいけない。私は判断するのが苦手だったし、多方面に目配りするのも苦手だったので、決定的に自分が不得意な分野に行ってしまったんです。
今思えば、私は人と働くというより1人で徹底的に読むほうが向いているので、その当時の何かニッチな分野を探すことができたかもしれないし、ローヤーズローヤーみたいな、ここは私の城ですというものが作れたかもしれない。多分全然違う方向性もあったと思うんですが、ロールモデルになるような人を探したり、事務所の中で1人でも自分の味方を探したりということもできなくて、自分が今落ちこぼれて困っている、惨めな状態にあるということを言えなくて、ただひたすら自分1人で考えていました。
あと、当時私は、「圧倒的な量をこなせる。」と評価されていて、とにかく量を増やそうと思っていたので、あの時期が一番つらかったです。あらゆるパートナーのアサインを受けて、受けて、受けまくって…デューデリとか24時間の限界までやっていました。自分から「開示をお願いします。」と質問を出しながら、開示がなければ「開示はされなかった。」と書いておけばレポートになるので、「お願いだから開示しないで、開示しないで。」と祈るような日々だったんです。あれはきつかったです。当時はいつも夜半過ぎに泣きながら帰っていました。仕事を受ければ受けるほど、新しい仕事に着手する時間が遅くなる。私としては速く作業していても、パートナーに返すスピードは鈍っていって、自分としては限界の限界まで働いているのに、評価はどんどん下がっていく。私がかつての自分に言葉をかけるとしたら「仕事は絞ったほうがいい。自分は量だけでなく質の高い仕事もできるということを示すことができれば、もっと違うレベルの仕事をもらえるかもしれない。」と言います。
私は自分の弱さに向き合うのが難しかったんだと思います。極度に強がる部分と脆い部分を持っていた。自分自身が弱いということを認めるのが思った以上に難しかったように思います。
家族法の研究を通じて得た「家族」についての視点
山口先生は家族法を研究されているということで、家族について伺います。
山口先生は「婚姻関係にある両親と子ども」で構成される“普通の家族”だけでなく多様な家族観を肯定されています。他方、家族観は多様になっても、「家族」を構成する普遍的な要素があるとのお考えを拝見しました。その普遍的な要素とは何でしょうか。
私はそれを研究テーマにして博士号を書いたんですよね。今の時代、違いを見つけることは簡単ですが、むしろ「普遍的な親子の要素」があるのではないかということで、それを父子関係で考えようと思ったのが私の博論のテーマなんです。
今アメリカでは様々な「父親」がいて、何を父子関係の基準にするかというと、婚姻・血縁に限らず、例えば生殖補助医療の分野では「意思」を基準にしますし、シングルペアレントが増えるにつれて、母との婚姻関係も子どもとの血縁関係もないのに子育てを手助けする人が注目され、「機能」を基準にするという考えもあります。ただし、全てに共通し得るものとして、「母親」がいるということです。親子法もこれを前提としている。そして、非常に例外的な場合以外は産んだ人が母になる。この「母子」との間に、「親」として第三者が関係に入ることについて何らかの合意があるべきである。
そこで、私は「父の三要件」というものを考えました。第一に、この人を親としてこの子どもの人生に招き入れます、という何らかの合意があること。それは、かつては婚姻だったのが今は婚姻じゃなくてもいいんです。第二に、子どもとの関係に何らかの継続的な関係が既にあるか、継続的な関係を築き得る基盤があること。それは、かつては血縁でしたし、今は血縁じゃなくて継続的に親として役割を果たし続けているということでもよい、とアメリカではなっています。第三に、外形的に見てこのユニットを家族として第三者に表示していること。この三要件が、かつての婚姻による父子関係と、今新しく生殖補助医療などの分野で形成される父子関係に共通する基準ではないかと考えています。それがより普遍的な父親、より性中立的に言うと「第二の親」の要件かなと思います。
「家族」は、婚姻ではなく、親子の関係から考えたい
父が親となる合意は、最初は“母親たる者”と結ぶことになると思うんですが、その合意は後から崩れる場合もあると思います。これは外形のユニットにも同じことが言えると思います。そういったことを想定すると、普遍的な要件を検討するのは難しい場合もあるようにも思えます。
親子法を見ると、子どもに対する「プライマリ・ケアテイカー」を1人確保することが、家族を考える上で、最も根本的な要素になるんですね。それは多くの場合は母になります。私はフェミニズムも勉強していたので、男女はなるべく平等であるべき、とは思っています。ですが、どの子どもにも可能な限り親というリソースを確保するという観点からは、その子どもを産んだ人という争いがたい存在が出発点となるのも事実です。
いずれにせよ、第一に子どもの責任を持つべき人がいて、あとは誰かを“プール”すればいいんです。つまり、「プライマリ・ケアテイカー」以外に子どもを経済的、精神的に支え得る大人が複数いてよい。例えば、アメリカではレズビアンカップルで男性が精子提供している場合もあって、そういったとき、3人以上の親がいてもよいという法制もあるんです。
日本は、明治以来フランス法の伝統を引いて、婚姻、つまり夫婦関係を家族の中心に据えていますけれども、私は「親子」を中心にするべきじゃないかと。子どもというのはケアしないと育たないので、ケアされる対象とケアする人を家族の基盤とする。ケアされる人とケアする人、そしてその経済的な脆弱性を支え得る他の人たちをいかに効率的に配分するかというのが家族法の基盤にあるべきじゃないかと思っています。
「プライマリ・ケアテイカーの支え」が弱くなったときも、“プール”された人が多ければ多いほど色々な選択肢がでてくる訳ですね。
そうです。この人が駄目だったら、入れ替わるということがあってもいいんじゃないかと思うんです。
ただ、経済的な脆弱性を補うためとはいえ、“プール”された人が何人もいると、個々の立場が不明確になる可能性もあると思うのですが、その点はどのようにカバーしていくのですか。
賛否両論あるかもしれませんが、私は、1人だけ「プライマリ・ケアテイカー」がいれば十分だと思っています。
たしかに、アメリカでも多くの場合、男女2人の親という家族構成が選考されてきました。
でも、アメリカの親子法は、子どもに対する圧倒的な責任を親に課す代わりに権利を与えるという仕組みになっていて、親の立場は非常に排他的。その排他的な立場が責任の所在を明確にしてきたと思うんですね。
そうであれば、「プライマリ・ケアテイカー」が1人いて、その人が責任を持つことが明らかになれば、子どもに対してもう少し開かれた関係があってもいいんじゃないでしょうか。例えば、宗教上の二世や三世となった子どもが家庭の中に囲い込まれるという問題がありますが、その場合でも、様々な生き方の可能性を提示することができますし、リソースが多いというのは悪いことじゃないのかなと思っています。

家族とは何かを考え始めたきっかけ
“普通の家族”以外の家族観を掘り下げることはすごく興味深いです。
山口先生が、“普通の家族”とは何なのかということを考えるきっかけは何だったのですか。
弁護士を辞めた頃の私は、エリート街道から退場するなら結婚か留学しかないだろうと本当に考えていたんです。それで婚約して留学した。なのに婚約を破棄されて…当時はマジで踏んだり蹴ったりでした。
今まで自分で人生を選び取るんだと思って生きてきたのに、結婚するときには選ばれなきゃいけないということで、自分を相手の物差しに入れていくわけです。色々努力をしたのに、それでも選ばれなかった。それは私をかなり傷つけたんです。
そんな時期に、ハーバードでたまたま時間が余っちゃって家族法の授業を取ったんです。めっちゃ面白いと思って、雷に撃たれたように聞き入ったんです。家族法の授業で自分の抱いたつらさは全く解決されなかったけれども、自分よりも以前に同じ悩みを抱き続けてきた人がいるんだということが分かって、すごく心が軽くなったというか、大きな連帯の中に私もいるんだな、それでいいんだなと思ったんです。
そこから家族法を研究したいなと思って今に至るので、家族法と出会ったのは偶然でしたね。
まだ日本では浸透しない生殖補助医療とその規制について
札幌高裁が*1同性婚を認めないことについての違憲判断を下したように、日本でも、多様な価値観が浸透している面があると思います。ただ、代理懐胎等の生殖補助医療については、アメリカほど議論は進んでいませんよね。
今の日本の家族法制の生殖補助医療やその規制の在り方については、アメリカと比べて、どのように感じておられますか。
おっしゃるように、最近の最高裁のトランスジェンダーに関する判決や、同性婚に対する裁判所の判断は、正に司法の存在意義が前面に出ていて、法律を学んだ者としてすごく嬉しいというか、頼もしく思うところがあります。
生殖補助医療については、民法の特例に関する法律*2ができてから、婚姻したカップルで、かつ、無精子症やターナー症候群*3のような、医学的に自らの精子や卵子で妊娠できない場合に限り精子や卵子の提供を認める、といった方向での議論が進められていて、それは多分、現状実際に行われているものをさらに狭めうるものだと思います。でも、人が子どもを持ちたい、という意志は多分止められない。そこで、日本ではできない治療を受けに海外へ行く人が増えていくのですが、それは、より危険でよりお金がかかること、より闇に潜ることだと思います。日本の規制の方向性が本当に今の状況を改善できるのか、極めて疑問に思いますね。
また、例えば不妊治療で結婚と事実婚のみに助成をするということになったとすれば、逆にシングルペアレントや同性カップルを国は推奨しません、という一定のスティグマの中で生まれてくる子どもたちを作ることだろうとは思います。そこは日本の家族法のある程度の保守性を反映しているなという気はします。
一方で、アメリカ法ってすごく適当なんですよ。法律をどんどん作るけれども、矛盾する法律を誰も消さないままで放置したりする。アメリカの家族法は最高裁判例がほとんどない分野で、完全に州法の範疇なんです。ワシントンとかカリフォルニアは家族法のリーダーになりたい州で、そういう州が新しく法律を作ると、各州がどちらかの州をモデルとして追随する。そして、多数決みたいな感じでカリフォルニア州モデルが人気になると、ワシントンは2年後ぐらいにしれっとカルフォルニア州モデルに直している。いわば民主主義の巨大な実験場で、各州が競って法律を作っていて、チャレンジを全く恐れない。日本だと、国を挙げて実験場にするというのはちょっとどうでしょうね、やっぱり議論を慎重にして、となりますよね。
アメリカがいいとは言いません。卵子提供にしても、あんなに市場に任せてどうなんだとは思います。市場に任せきりにした結果、代理懐胎と比べて卵子提供のほうが労務に比して高額になっていて、卵子が何百万円とかで売り買いされる。それは人が遺伝子を求めるからです。代理懐胎者はしっかりした人ならそれで十分だけど、自分の子どもの遺伝子になるんだったら美人で成績がよくて…みたいな感じになってくるのが市場の嫌らしいところだと思っていて、それが全然いいとは言わない。でも、日本は家族法の改正にこれだけ慎重で、夫婦別姓も1回失敗してからこれだけ長くかかってしまっている。そこで、海の向こうで行われているアメリカの巨大な実験を見て少し参考にするというのもいいのかなとは思います。
※1 インタビュー当時。令和6年10月30日には東京高裁で、令和6年12月13日には福岡高裁でも違憲判決が下された。
※2 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律(令和二年法律第七十六号)。
※3 性染色体である「X染色体」が欠失、または一部欠失などの構造変化があることで生じる遺伝性疾患の総称であり、自然妊娠が極めて困難となる。
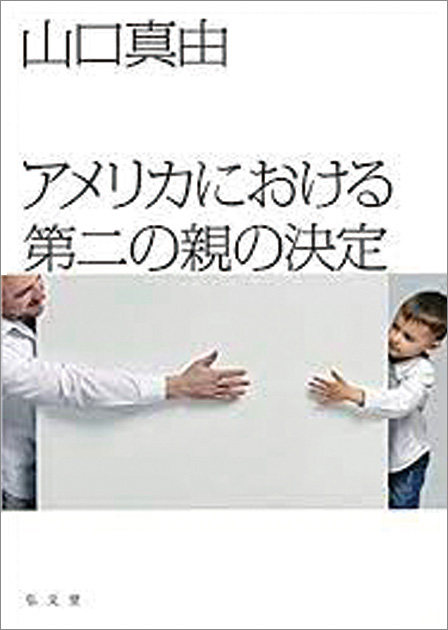
卵子提供は今後、どうあるべきか
日本では卵子提供は公的には認められていませんが、対価も含め今後どのようにしていくべきかについて、お考えはありますか。
非常に難しいと思います。労務の対価はあるべきだ、というアメリカの考え方も合理的だと思います。
当初、アメリカでは、精子提供に対して卵子提供は56倍の時間がかかっているというデータがあって、精子提供のお金の56倍の対価は支払われるべきであるから、5千ドルを上限とし、正当な理由があれば1万ドルまで認める基準を学会が作りました。今は、それが独禁法違反になって取り除かれて、市場は無制限になっています。あまり対価が高額であると、利他性みたいなものが薄れるのではないかという研究もあるので、高額すぎる対価はよくないかもしれません。
でも、日本ほど厳格に対価を排するのもどうなのでしょうか。忙しい中で時間を作って、クリニックに並んで、卵子を提供するという労力に対して無対価を想定するのは非現実的な気がします。やはり時間を作ってやることなので、それに伴う何らかの対価、あまり商業的にならない程度の合理的な対価は許されてもいいのではないかと思います。
対価を設けることは必要だと思います。それに加えて、その親の学歴や容姿はどうなのかという話が上がって、そこからまた差別が生まれるという問題も残っているのではないでしょうか。
アメリカでは、卵子提供では卵子提供者の写真が出されるんです。そうすると、やっぱりきれいな人のほうが購入希望者が集まりやすいです。これは非常に優生主義的でよくないと思います。
しかし、精子バンクでは必ずしも1人に集まるわけではないんですね。自分のパートナーに似ている人がいいとか、声を聞いてこの人がいい、とかです。オールAを取っているとか、スポーツ万能みたいな、特定のスーパーマン1人に集中しているわけじゃないので、精子提供においては優生主義に対する一つの反論が提示されているのかなと思います。
でも、子どもに最善を望むのは親の愛すべきエゴという側面はやはりあると思いますし、そのエゴを一概には否定できないですよね。
それはそうとして、今のアメリカを見ると、卵子提供の病院にしろ精子バンクにしろ、野放しになっているので、そういう中間機関がきっちりとしたマッチングをさせる仕組みを作っていく必要はあると思います。
写真を並べられたら、自分と似ている卵子提供者を選択してしまう人も多そうです。
でも、育てていくということ自体に価値を見いだす人はいらっしゃると思います。私は自分と似た子どもを育ててきたわけですけれども、全く違う子どもを育てるというのも、面白いのかもしれません。自分と似たところがあると、逆に自分と違うところばかり探すじゃないですか。何でこの子は勉強しないんだろうなとか、何でこの子はできないんだろうなとか。全然違う子で、すごい運動神経抜群とかだったら、それはそれで親子関係としては新しいのかもしれないと思います。
なるほど。そう考えると、卵子提供でなくても養子縁組でよい気もしますね。
それもよく言われますね。なぜ卵子提供じゃなきゃいけないんだというのは一番深い問いなんでしょうね。
考えられるのは、アメリカにおいては養子縁組のプロセスが、子どもの利益を優先するという名の下に、親に対しては相当ハードルが高いものになっていることです。
もう一つ理由を挙げるとすれば、速やかに低年齢のうちで養子縁組をすることが、その後の親子関係にとってプラスになるのですが、それがなかなか難しい状況にあります。新生児は、プライベートアダプション(private adoption)といって、弁護士が介在しますが、妊婦に対するケアという形である種の対価の支払いに近い形のやりとりがあるとされます。なので、養子縁組にいいイメージを持っていない方はいらっしゃるかもしれません。

自身の子育てについて
山口先生は昨年、ご出産されましたけれども、子育てについて工夫されていることや苦労されていることはありますか。
私は周りにすごく恵まれていて、保育園もすごくいいところで、子どもの個性を考えて伸ばしてくださるし、安心して預けられるんです。
それよりもむしろ、働くことと子育てとの物理的な両立はかなり難しいなと思いました。仕事中にお迎えの電話が来たらどうしようという不安は常に抱かなきゃいけないので。女性活躍とか色々言われますけれども、仕事と子育てを両方やるというのはまだかなりハードルが高いなと思います。
それに、今の社会は、子どもを持っていることに対するネガティブなことを共有することが多くて、よかったことを共有することが結構難しいですね。例えば、子どもが病気になって大変でしたというのは、賛同は得やすいです。でも、自分と全く違うものが大きくなって成長していくということのほうが私はすごく楽しいなと思っています。子どももできることがどんどん増えていくし、私自身も自分と別の人格を受け入れていくという過程で大きくなっていく、育っていく部分があるんですよね。
基本的にはすごくつらいけど、今一番わくわくします。子どもが産まれる前までは、旧態依然とした家族観と闘おうとか色々大きなことを考えたんですけれども、子どもが産まれると、この子が健やかに成長してくれれば別にどっちでもいいと思えるので、自分としては面白い変化だなと思います。
山口先生は東京や大阪といった各所を行き来されておられて、どのように仕事と子育てを両立されているのか、皆さんも興味深いのではないかと思います。
日々戦いです。例えば、名古屋でのレギュラーの生放送の場合、いつも乗る新幹線は17時57分に東京駅に着くので、そこからダッシュすれば18時半のお迎えに間に合うんです。でも、昨日は、地震が起きて新幹線が停車したんです。遅延がどのくらいかによって、保育園を延長する必要があるのか、シッターさんにお願いする必要があるのかということが変わってくるので、そこはいつも綱渡り状態です。
シッターさんに頼っているところもあります。いろんな人に来ていただいて、すごく信頼できる方が何人かいらっしゃるので、その人たちに助けてもらっています。私は、自分たちの力だけじゃなくて、いろんな人に助けられて子どもを育てようと思っていて、だから、母子を支える人たちがもっとたくさんいてもいいのかなと思っています。子どもが親だけをロールモデルにしなければいけないわけじゃないだろうと思います。
先ほどの「プライマリ・ケアテイカー」と、その周辺を補完し合う人たちというお話にも繋がりますね。
そうですね。働きながら子どもを持つというのは難しいので、それを支える人はもっとたくさんいてもいいし、そのほうがむしろ安定するんじゃないかと思います。
忙しい日々での「学び」について
弁護士でも留学したりして学び直しをする人もいますし、常に改正法をフォローアップする必要もあります。山口先生は、時間がない中でどのような学び直しの工夫をされていますか。
私は黙っていると結構サボってしまうほうなのですが、今はワイドショーなど出演番組のテーマが様々なんです。私はテーマが与えられるとそのテーマに関連する本を読みます。何冊か本を読んで、自分なりの問題意識ができて…みたいな形です。意識的に勉強する時間を作るのは普段すごくお忙しい方々にはかなり難しいと思うので、やらなきゃいけないことができたときに、ここで十分だけどもうちょっとやる、というプラスアルファでやっていくのが少しずつ蓄積になってくるんじゃないかと思います。
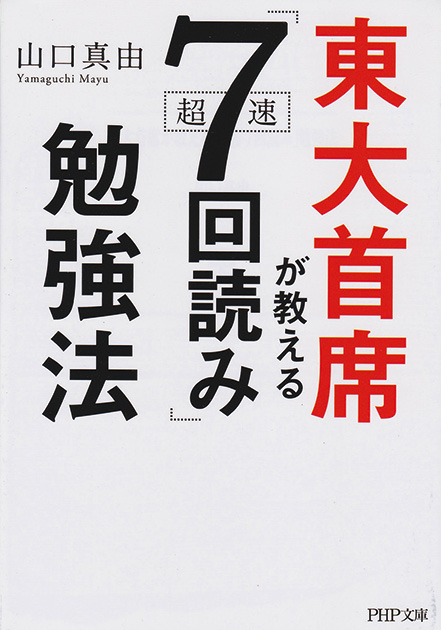
メディア出演時の心がけについて
コメンテーターの分野のお仕事について、人を引きつけるようなコメントをお話しされるために山口先生が心がけていらっしゃることはありますか。
参考になるか分からないんですけれども、人って絵が浮かばないとインプレッションがないんです。だから、なるべく具体的なエピソードで絵が浮かぶかもしれないというものを準備しておくんです。
人って、先生方のように抽象的思考に慣れてなくて、具体がほしいんです。だから、これなら絵が浮かぶかもしれないという具体を3個ぐらい用意しておくんです。4個、5個あると自分も向こうも混乱しちゃうので最大3個で、出せたら出す、出せなかったら持ったまま帰るというのがすごく大事です。無理やり出そうとすると、強引にやったなという印象を与えてしまうので、持ったまま帰るという覚悟が大事です。
でも、先生方はそういうお仕事じゃないですもんね。訴訟は具体を抽象化するという仕事なので、これはあまりお仕事には活きないかなと…。
いえ、山口先生に憧れている弁護士は非常に多いと思います。
マジですか!!
メディア等で異業種の方と一緒に働くというのは弁護士にとっても非常に勉強になると思います。
ありがたいです。弁護士の先生はメディアの世界まで下りてこないだろうというイメージを持っている人が多いと思いますし、弁護士の先生方の中でも、例えば広告を打っている法律事務所はどうなんだろうと思っていらっしゃる方もいらっしゃるんだろうと思うのですが、困ったときに躊躇なく相談できる身近な弁護士というのがもっと増えたらいいなと思いますね。
今後の将来像について
山口先生はいろんなご経験を積んでこられたと思いますが、これからこういうことをやってみたいとか、次の目標はおありですか。
私はそういうのがあったことがないんです。常にその日暮らしです。今日ベストを尽くして寝て、また明日ベストを尽くそうというのを繰り返していて、それがずっとコンプレックスでした。目標は何ですか、長期的な視点は何ですかと聞かれて、答えることができない。でも、私は今、家族法を研究しながら、自分の家族を何とか日々やりくりして運営している。それがどこに繋がるかというのは、正直全く分からない。でも、それにベストを尽くし続けたら、その先に何かがあるんだろうと信じて、日々帰納的にやっていくしかないのかなというのが今の感覚です。

若手弁護士や法曹志望の方へのメッセージ
最後に、これから法曹になろうとしている人たちと若手の弁護士に向けて、山口先生のご経験も踏まえて、気を付けるべきところや期待することなどメッセージをいただけますか。
私の経験を踏まえると、皆さん弁護士になられて、そこから自分が行った場所に自分の居場所があればいいですけど、そういうことって実はあまりない。行った事務所がすごくよかったというのは偶然でしかなくて、事務所に合わなければ辞めるか残るか、みたいな極端な話になりますよね。
でも、弁護士にはいろんなお仕事があるから事務所の中で開ける未来が本当はある。少なくとも私はそうだったので、自分が今困っているということを経験豊富な弁護士の先生方に言えば、同じ道を通ってきた人が何らかアドバイスをしてくれると思います。弱さを出すことは必ずしも弱いことではないと思います。
私は法律というものにすごく抵抗があって、東大で、初めて法律の授業を聞いたときに、「あ、失敗したな。」と思ったんです。若いときは民法がすごく冷淡だと思ったんです。「悪意って、別に悪い人でもないのに、ちょっと隙があるということをあれだけ許さないというのはおかしい。」と思ったんですけれども、当時の民法の先生が、「民法というのはある種のフィクションである。それは自分の頭で考えることができる市民によってすごく単純化された形のフィクションであって、実際の人間はそうは動かない。みんな弱さがあって、不合理な動きをする。だから弁護士というのは社会と法律の架け橋であるべきだ。」とおっしゃっていて、弱いかもしれない、不合理に動くかもしれない人間を、合理性が想定される民法と繋ぐのが弁護士なんだなと思ったんです。それから弁護士という職業に対して温かみを感じられるようになったんです。今、法律家というものは遠いとか冷たいというイメージをお持ちになっている方もいらっしゃるかもしれませんが、法律に血を通わせることができるのが先生方の毎日のお仕事だと思うので、そう思って法曹の道を歩み出されるのがいいのではないでしょうか。
本日は、お忙しい中、大変貴重なお話を伺うことができました。ありがとうございました。
こちらこそ、ありがとうございました。
2024年(令和6年)8月9日(金)
インタビュアー:折田 啓
尾崎雅俊
国本聡子
豊島健司
中務未樹
松田七海