弁護士会から
広報誌
オピニオンスライス 6月号
-
産業医・医療ジャーナリスト
平野翔大さん
HIRANO, Shodai
産業医・医療ジャーナリストとして活躍される平野翔大さんにインタビュー。制度の構築は進んでも実態が伴っていない男性の育休のほか、男性がどう子育てに関わっていくべきか、男性にどう子育てに携わってもらうか、男性・女性両方の目線から教えていただきました。
-

これまでの経歴を振り返って
平野先生が産婦人科医を目指されたきっかけを教えていただけますか。
高校が付属校だったので、進路は「どの大学」ではなく「どの学部」という選択だったのですが、最初は主に法学部や経済学部を考えていました。ただ進路選択になって、自分がやりたいことを考える中で、人とダイレクトに関わるのが面白いだろうなと思って、医学部という選択をしました。
教育にも興味があったのですが医師から教育の道に転ずることだってできますし、まずは手に職をつけるという意味で、医師免許を取りに行こうと思って、医学部を目指しました。
産婦人科を選んだ理由ですが、医学は最初に生理学と解剖学のおおむね2つに分かれるんです。人体構造を物理的に捉える解剖学と、ホルモンなど化学物質的に捉える生理学があって、どちらかというと生理学のほうが好きだったんです。産婦人科は女性ホルモンを主に扱う上に、手術もするし、不妊治療もするし、外科も内科も手広くやれる。
総じて選択に迷った時は自分の可能性をあまり狭めないように、いろんな選択肢を取っていこうとしてきたのですが、それが今の活動にもつながっています。
今、メインでされていることはどのようなご活動ですか。
臨床ではなく産業医になります。健康管理的な仕事ではありますが、大企業を担当しているので、例えばハラスメントがあれば、聞き取りをどうするかとか、トラブルの原因に病気は絡んでいないかどうかを検討するというような立場でして、労務に関するご相談を受けることは多いです。労務系の弁護士さんともすごくお付き合いが多くなりまして、自分は本当に医療職なんだろうかと思うこともあります(笑)。
ジャーナリストもされておられますが、これはどのようなきっかけで始められたのですか。
ジャーナリストになったきっかけは、研修医時代の発信ですね。元々、文章を書くのが好きだったんです。
長野県を直撃した台風があって、新しくできた新幹線が沈んだというニュースを覚えていらっしゃいますか。あの時に私はちょうど長野市にいたのですが、新幹線だけでなく、実は結構な数の病院が沈んだんです。信濃川(千曲川)のほとりの病院で1階部分が沈みましたという病院がたくさんあって、私はそういうところの患者を受け入れた内陸側の病院に勤めていたので、そこで災害医療というものを目の当たりにし、まさにホールにベッドを並べて患者を寝かせておくみたいな状況を見て。そこのありのままの景色を伝えたいと思った時に、たまたま縁があって伝える機会をいただきました。それがすごく読まれたのがきっかけでしたね。
平野先生が代表をされているDaddy Support協会の設立の経緯を教えていただけますか。
産婦人科の現場にいると、接するのは当然ほぼ女性です。女性と接しているといろんな問題に遭遇します。分かりやすい例で言うと、とある飲食店で働いている方でしたが、男性の上司の理解がよく及んでいなくて、おなかが出ていなければ大丈夫と言って12キロの荷物を運ばされて切迫早産になったとか。因果関係は不明ですが、そういった周囲の男性の不理解みたいなことをすごく感じていました。私は、元から患者だけを診るというよりは、その背景にあるものが気になるタイプだったので、そういった男性の不理解がどうにかならないのかなということをずっと心の中で思っていました。
その後、産婦人科医を辞めて産業医になったのですが、そうすると企業内の男性の問題が見えてきました。元産婦人科医ですという立場を明かして企業内で産業医をやっていると、育児の相談が来るようになります。女性からももちろんいろんな相談を受けましたが、面白かったのは男性たちで、育休は長くなくて、早々に育児と仕事の両立という問題に直面して悩む。こんなに両立が大変だと誰も教えてくれなければ、分かる環境もない中で、彼らは手探りですごく苦しんでいる。結果として、頑張ろうとしてうまくいかなくなって鬱になってしまったお父さんもいるし、多分パートナーを困らせているお父さんもいる。
このお父さんたちを誰が支えていたんだろうと考えると、誰も支えてこなかったんですよ。国は育休を取れ、育児に参加しろと言うけど、育児ができるようにしてくれる人が誰もいないわけです。この状況を変えなければならないということからこの活動が始まりました。知り合いづてにいろんなお父さんに話を聞き続けて、その中の何人かが一緒にやりたいと言ってくれたのもあって、協会という形で設立をしたのが2022年です。
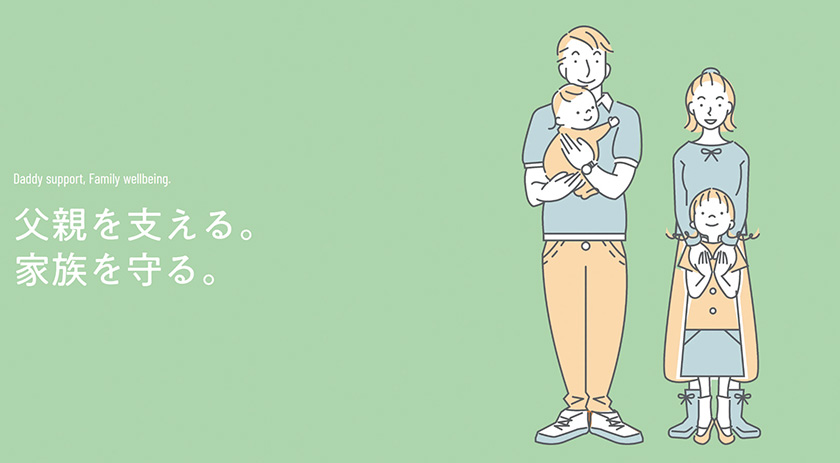
結局、本質を伴っていない男性育休
制度は充実しているけれども支援が足りないということですよね。では、これから具体的にどんな支援をされていこうとお考えですか。
例えば、「母子保健法」という法律がありますが、名前からして駄目なんです。妊娠・出産だけじゃなくて、出産後の乳児健診とかその後のケアまで全部規定する法律なのに「母子」なんです。要は、本当に女性しか対象にしていないんです。
ゆえに、例えば自治体がお父さんに対して何かしようと思ったとき、自治体は法律に基づいて動くので、誰がやるんですか、どこがやるんですかから始まってしまう。企業にしても、例えば企業内での育児支援といっても、保育とかやってたらいい会社だよねくらいの感じで、専門家の助産師や保育士も在籍していなくて、経験値がない。そんな中で、「何とかいけるっしょ」という本当にこのノリで育児に突っ込んでいっているので、もうこのシステム自体を変えていきたいと思っています。
とはいっても、そんな大きな仕組みをいきなり変えるわけにもいかないので、例えば自治体でサポートができる事例づくりをやったり、そういうことから始めました。
育休を取れば済むという問題ではないですしね。
そうなんです。休みを取ったら育児ができるわけではないし、休みと思ってごろごろする人が出てくるというのもおかしい。ですから、東京都が「育業」と言ったのはすごく言い得て妙だと思います。仕事だったら、スキルゼロの者を現場で使うことなんてできないわけじゃないですか。それと一緒で、育児もトレーニングしなきゃいけないのに、そういう話が全く出てこないんです。
積水ハウスは育休を取るときに夫婦でちゃんとこれからのことを考えましょうという紙を出させたりするそうで、これを全国でやらないといけないという話ですね。
そうですね。予め会社がプランニングの準備を支援する、ああいうのはすばらしいと思います。ただ一般化するのはすごい難しさを感じます。行政は色々な価値観の人たちを相手にするので、一筋縄ではいかないというのが今行政と一緒にやっていて感じるところです。
行政の方も、旧態依然とした価値観を持っておられる方が多いですか。
行政の中でも前面に立っている助産師とか保健師の考え方はすごく変わってきています。お父さんが目の前に出てくることが増えましたし、最近は行政からの研修依頼もすごく増えてきたので変わってきたんですけれども、問題はその上の層の人たち-制度設計に携わる人たちです。こども家庭庁は未だに「母子保健」を掲げてきますから、まだまだ父親を主体に考えるということはあまりないような状況です。
労働時間の問題についてはいかがでしょうか。
女性にもっと働いてもらわないと就労人口が減って困るから男性も育児してねという意識で、男性育休の取得を推し進めてきたわけですが、そこがそもそも間違いだと思っています。今、働き方改革が始まって、男性の育休取得日数は1か月ぐらい伸びましたが、女性の育休取得日数は一切縮んでいません。要は、男性が育休を取ったからといって女性の育休期間が減るわけでも何でもない。男性も育休を取って、男女の労働時間のバランスをどう取っていくかという問題ではなくて、既に女性が限界を迎えていたということが抜け落ちています。
もう一つは、育休から復帰してからの問題ですよね。女性が育休を取って家で一応専業主婦になっている期間があったとて、男性が育児に参画しようと思ったら残業はそもそも難しいはずです。特に共働きで復職なんてしたら、残業していると家庭は回らない。こんなことはちゃんと計算したらすぐに分かることなのに、企業もそうですし、法律上も、育休を取らせるまではいいけれども、育休後の働き方はあくまで自発性に任せている。結果として、女性は当たり前に時短、男性は当たり前に残業という文化は続き、育休後の家庭内の労働時間の分担もうまくいっていないですね。
子育てについて「知る」ということ
今、子育てがつらいというネガティブな情報がSNSで発信され過ぎていて、出産をしていない人や、これから出産を控える人からすると、そんなに大変なのと。これを仕事をしながらやるのか、という恐れみたいなものが生まれやすくなっている気がします。そういう方に何かアドバイスはありますか。
知らないから怖いんですよ。知らない理由は教育の怠慢で、計画できないのもそうじゃないですか。プレパパ教室などでは、子どもは予想できない勝手な動きをするものだから、計画どおりにはいかないけど計画は立てたほうがいいと言います。要するに、計画を立てて余裕を持っていればバッファーがあるので吸収できるわけですが、計画を立てずに場当たりでやり続けると絶対に余裕がなくなってくるので、ちゃんと知って計画を立てたほうが絶対に楽しく育児ができますよと。我々もネガティブ情報を出す側になりやすいんですが、ネガティブをちゃんと知っておくことが、最後ポジティブを楽しんで終えるコツだよねというふうになるべく結論づけるようにしているぐらいです。ですから、一番は、ちゃんと妊娠・出産の段階から、性というところも通じて育児を教えていく、知るということだと思います。妊娠、出産、育児は、最後は踏み出してみて、徐々にリアルな感覚を持って実際挑んでみたら、用意と知識さえあれば何とかなるものだということであってほしいなと思います。それも含めての支援システムが足りていない、それはこの国の大きな課題です。
もう一つあるとすると、どんな楽しいことでも拘束されたら楽しくなくなるじゃないですか。その考え方もすごく大事だと思っています。やっぱり育児も楽しいんですよ。ただ、24時間拘束されるとつらくなる。自分の時間がなくなってしまう。育児を楽しむコツは、自分の時間を持つことです。計画と言いましたが、夫婦ともに自分の時間を取って、自分の睡眠時間が取れるように計画を立てておいて、最悪、子どもが熱を出したときにその自由時間や睡眠時間が飛んでいくことはあっても、普段が維持できていれば何とかなるんですよね。ちゃんと知っておくことと、拘束はされないこと、というのが育児を楽しむ上で大事なポイントだと思います。
ほどほどでいい
「♯ほどほど育児 失敗したっていいじゃない」という本がありますが、あれはめちゃくちゃいいなと思います。よく言ってますが、ほどほどでも子どもは死なない。要点を押さえれば死なないです。それも知識じゃないですか。例えばミルクを常温でつくろうとする人、はちみつをあげちゃう人などは子どもを殺しかねないのでやめたほうがいいと思いますが、そういうところさえ押さえておけば、多少のことで子どもは死なないです。そういう観点を持っておかないと、「ミルクの量が少し違うだけで将来に影響する」のように強迫的な観念に駆られた育児をする人がすごく多くなったなと思うので、それも怖いの原因になっているんだと思います。
受験勉強と一緒で、みんなこれしかやってないんだみたいな。そういう横のつながりをつくることは本当に大事ですね。
みんなと同じことがちゃんと分かっていて、常識的な問題に答えられていれば、みんながミスる問題はミスってもいいというスタンスはすごく大事かなと思います。
やっちゃいけないを知らせるのは、やっぱり公教育だと思います。もちろんみんなの中で共有していくのもいいですが、知識としてやるべきところは本当は公教育がやらなきゃいけない。そこがすごく欠如しているという危惧は抱いています。
「公教育の必要性」~男女で異なる学びのアプローチ~
妻が教えると、夫としてはちょっとむっとする、何でそんなこと教えられるの、みたいなことを思う男性が多いようで、公教育の必要性は実感します。
教育スタイルを変えなきゃいけないのに自治体ができていないんです。一般的に、これまで女性向け情報として展開されてきた育児情報は「こうやればいい」と、実践的・感覚的に情報が共有されます。個人差はありますが、多くの男性にそれをやると「そういうことを言うのは分かるけど何で?」という気持ちになり、感情疲れを起こしてしまいます。こういう理由があるからこうだよという知識と理由をちゃんと教えてあげるとすっとやるんですよね。ここの情報アプローチというのは育児界隈では非常に乏しくなっていて、ふわっとしたものばかり与えられるのでストレスフルに感じる男性は実は多くて、こういうところは改めて整理して、体系立ててお伝えしていくのはまさに教育の役割だろうと思います。
実際、公衆衛生の研究でもあるんですが、育児関連で行動を起こすのに、女性は方法論から入っていくんです。例えば子どもにお薬をあげるときにどんなことを知りたいですかというと、お薬のあげ方とか吸わせ方というところから入るんですけど、男性は、病気と薬の知識を知っていることが上位に来るんですよ。全然違う傾向を示しました。ですから、先に方法論を教えちゃうと、男性側は「その方法論は分かったけど、何で?」という気持ちになってしまう。女性側は、どちらかというと、方法論からこうだからこうなのねという導き方をしていくという逆のアプローチを取るので、この辺はやり方を変えなきゃいけない。ここは自治体さんがやろうとすると、女性のものを男性に転用するので、それこそ年上のおばちゃんに説教されたみたいな気分になって帰るんですよ。で、もう二度と来なくなる。その辺はすごく大きな課題です。
子どもが生まれてきて男性の皆さんはどこに悩まれているのか、それにはどういうサポートが必要なのかということを具体的に教えていただけますか。
皆さん(弁護士)のクライアントと一緒かもしれませんが、男性たちはどこが分かっていないかが分かっていないんです。専門職だと基礎知識を持っていて、クライアントの課題を抽出したときに、ここの問題なんだなとある程度系統立てて整理することができるじゃないですか。育児でも一緒で、基礎知識があれば課題が抽出できるのですが、それがない中で手技をやらなきゃいけないんです。なので、自分はどこが分かっていなくて、何を押さえられていなくて、どこができていないのかを彼らは自分自身で分かっていないという状況です。それこそミルクのつくり方なんて要点となるのは知識ですが、やり方として学んでしまうので、全部そのとおりやらなきゃいけないとなって、あれはどうなってるんだっけみたいなところで苦労したり、ちょっと応用を利かせたときに、何か月の離乳食はこうだけど、7か月たったらこうしなきゃいけないとなったら、またどうやるんだっけみたいな感じの苦労をされている印象です。どこが分かっていないかというところからの課題を私はすごく感じます。
夫は言われたとおりにやらないとまた怒られると怯えてしまって、「こうやるんだよね?」と一々確認してくるんです。もうそこはある程度自由にやってくれていいからとこっちとしては思うんですけど…。
少しやり方を変えたつもりがやばいところを踏んじゃって、「それ違うねん!」となるという、そのはざまが分からないんです。方式として整理しちゃっているので、「え?何でここは駄目だったの?」みたいな気持ちになるわけです。
抱っこのやり方も、赤ちゃんの首が据わっていない段階での抱っこというのは、首を落としちゃいけないので、そこにすごく気を使うんですよね。首が据わってくると別にそこは気にならなくなりますが、今度は身体がでかくなってくるのと、さらに、歩き出すと、肘内障といって、子どもの肘は未熟なので万歳したら肘が抜けちゃいますから、そういうところに気をつけなきゃいけないんですが、立たせるために引き上げるという動作を大人がしてしまって、これは駄目だよねと。だから、今は駄目だけど、何か月たったらもう大丈夫みたいなものもあるので、この辺のベースを知っていると、このぐらい育ってきたからもうこれは許されるかなとか、この辺はもう適当でいいかなと分かるじゃないですか。男性側はまさにここがないです。
ここまで男性の側に育児の基礎的な知識がないことを伺ってきましたが、女性はこういった点を学ぶ機会があるのでしょうか。
女性の側にも学ぶ機会はあまりないです。親にこれぐらいだと大丈夫だよと言われて、何となくそうなんだと思って育児をされている方が多いのではないでしょうか。方法論から入って整理していくというのは女性のほうが得意なのだと思います。ただ、基本的なことを知っていれば不安に思わずに済む場面も多くあるので、女性の側にも基礎的な知識を学ぶ機会があるべきだと思います。

基礎的な知識を広める方法について
そもそも育児の仕方に疑問に思っていなかったり、何が分かっていないのかも自分で分かっていなかったら、助けを求めようということにならないと思いますが、そういった方にどのようにアプローチしていくのがよいのでしょうか。
我々は、基礎的な知識を父子手帳のような形でまとめる活動もしていますが、育児の要点というのは、普通の教育と違って本当に整理されていません。学問的な系統立ったものとして整理しなくてはいけないというところに苦労を感じます。
世の中の育児知識って結構間違ったものが多いんです。根拠も何もあってないというものが平気で転がっていて、訂正も大変というのも含めて、専門家とクライアントの関係性に近い部分はかなりあると思います。
ただ、育児というのは多くの人が経験する事象で、専門性が評価されづらいという難しい分野です。我々としてもどうアプローチしていったらいいんだろうという悩みがあります。
どのようなタイミングで基礎的な知識を身につけるのがよいとお考えですか。
豊島区で行っている事業では「妊娠期からの男性育児支援事業」という名前で男性への基礎的な知識の普及を行っているのですが、この「妊娠期から」というのがすごくポイントです。
どんな仕事もそうだと思いますが、OJTだと学習量がすごく減ってしまいます。系統立った知識を身につけるには、事前に一通りの基礎知識を身につけてから、OJTでいろんな知識を応用化させていくという順序を踏むのが望ましいです。育児においてこの基礎を身につける期間というのが、本来妊娠期のはずなんです。
準備期間があるというのはとても貴重なことです。例えば病気になる場合を考えても、病気の知識を事前に勉強できるわけではないじゃないですか。育児はこれができるはずなのに、男女ともその期間に系統立って学べていません。女性のほうはまだ自分の体が変わっていくので何となく自分の体の不便として妊娠を認知し、おなかが大きくなると勝手に周りから出産後に必要なことを聞いて、一応の知識を習得しているんですが、男性はそれもない。そのような状況でいきなり育児をしてもなかなかうまくいきませんよね。ですから、妊娠期に系統立ったものをいかに伝えていくかというのが一番のポイントだと思っています。
うまく育児ができている男性はどのような方ですか。
やはり妊娠期にしっかり準備をしている、あるいは、パートナーさんが教育し、育児の要点を身につけさせる場合にうまくいっています。こことここが要点だから、ここは押さえてきてと言ってやらせるわけです。そして、要点を押さえたお父さんが出来上がって、あとは随時妻が教えるみたいなスタンスだと結構うまくいきます。逆に言えばこのように女性がうまく教育し、手配できないとうまく回りにくい構図ができているわけです。教育をパートナー女性に依存しているということです。
出産後の家事なんて赤ちゃんもいる中でやらなきゃいけないので、片手間家事なわけです。よくある例で、産後に家事を始めて、スパイスからカレーを作り始めて嫌われる人がいますが、実際いきなり片手間で家事をしようと思ってもできませんよね。だから、妊娠中でゆったりしているときに、料理に1時間もかけてるのかこの人と思われながらも練習を始めて、出産した時点で片手間で料理しながら育児をできる状態に準備するんです。その余裕を取れるはずの妊娠期間にそれをやっていない。だから、家事も育児も全然知らない状態で、産後のお父さん1日目を迎えて、OJTしかない中で、家事もやり方が違う、育児もやり方が違うと突っ込まれ続けるお父さんが出来上がってしまう。
豊島区でも、これまでの父親向けのアプローチはほとんど産後でしたが、妊娠期からやっていくことが大事だよねということを豊島区も応援してくださって、事業を進めているところです。
2人目になると、子育てが一層大変になるように思うのですが、子どもが1人の段階で学んでおいたほうがいいことはありますか。
2人目のほうが楽という方のほうが多いですよ。1人目で基礎知識もある程度は整理されていて、何となくこれぐらいでいいんじゃないかという適当さが身についている。また、2人になると、否応なしに時間的制約が増えるので、周りに頼らないと絶対に回らない。そうなると、諦めて誰かに頼り始めるので、そういう意味でも負担が軽減される方は多いだろうなと思います。
学ぶことというよりむしろ、夫婦の間の価値観のすり合わせが大事だと思います。面白いことに、長く育児をやっていく中で育児にこだわるのは男性なんです。例えばお父さんは子どもの食事は手づくりのほうがよいとか、親がちゃんと面倒を見ていたほうがいいとかこだわる傾向が強いのに対して、お母さんのほうが、別にレトルトでいいんじゃないとか、多少人に預けたほうがいいんじゃないと、ある意味で現実を見ているんです。育児の期間が長くなってくるとこういう価値観の違いというのが育児スタイルの違いに如実に表れてきます。2人目となると、お母さんはより現実を見るようになるので、そうなったときに、お互いのどこのこだわりを捨てるかです。
あとは、1人目のときにしんどかったことを整理してみて、同じ状態にならないように準備することも重要です。
育児介護休業法の改正の影響について
育児介護休業法が改正されて、出産後に産後パパ育休の制度が設けられましたが、施行されて効果はあったと考えておられますか。
この法改正の最大の意義は、産後に育休を取ることが大事だというメッセージが出たことにあると思います。社会や父親自身が産後は休まなきゃいけないものなんだという認知を持った、これはすごく変わったことだと思います。産後の育休は、他の資源に頼りながらでも父親だけで子どものお世話をできるようにする集中トレーニングの期間だというスタンスの方がやや増えてきたかなと感じますし、そうであればこの産後の育休というのは非常に意味があります。
子どもが生まれてから、1日父親が育児をして、母親はどこかに泊まってこいというのをやってみるといいですよね。
そうですね。1日子育てを自分ですると、見えない家事が見えるようになるんです。自分が帰宅したときに家が散らかっているのがなぜかよく分かるでしょうし、例えばミルクをあげる前後にしないといけないことが全部見えてくる。この準備をしてないとミルクをあげられないんだと気づけば、効率よく家事の段取りを組むことにもつながっていくので、その辺はやってみることが大事です。
我々も育休中の過ごし方みたいな講習をやることがありますが、最終目標は24時間子どもと2人で過ごすことです。それを数日続けることのしんどさを知ってほしいし、とはいってもスキル的にはできる状況にしておくことが必要です。これしんどいなと思って気持ちよく仕事に戻っていくのがいいですという話はよくしています。
育児中に精神的に不調になるのはどういった場合でしょうか。
一番怖いのは、育児と仕事を両立していくタイミングです。やりたいと思っているのにできないもどかしさがあったり、それでパートナーからも「何でやらないの?」みたいなことを言われて、仕事のほうも増えてきてみたいな状況になると鬱になる危険性があります。
留学も出向も異動も、一番最初が一番大事です。最初に適応できないと結局その後も駄目になってしまうので、異動した瞬間にかなり手厚いケアをしますが、育児も同じで、育休から復帰するときにちゃんとケアをする必要があります。企業としてはその期間だけ見ればマイナスであっても、しっかりコストをかければ会社にとっても利益になるという考え方を持ったほうがいいと思います。
あとは、長期育休を取って社会から隔絶される人も鬱になる場合があります。育児って予定どおりにうまくいかないわけですよ。特に長期育休で閉じこもる場合には仕事もやっていないので評価されないんです。俺、駄目な人間なんじゃないかと自信を喪失していき、精神的に不調になる人がいます。
育児休業制度の本来あるべき姿について
大企業に、社員の育休取得に関してアドバイスをする際に、どのような工夫をされているのでしょうか。
企業が育休取得を進めることについて、企業にどのようなメリットがあるのかということを理論立てて説明するようにしています。男性社員に育休を取得させることは、短期的に見ると多くのコストがかかります。しかし、長期的な目で見たときには、社員に長く働き続けてもらうことができるようになり、将来に向けた投資となることを説明しています。
また、社員と管理職側の両方からアプローチを行うことも工夫のひとつです。例えば、育休取得を推進する中で、子育ては行わず単に休みを取るだけとなるなど、育休制度をフリーライドする社員も現れます。このような事態を防ぐためには、社員に対しては、企業に育休取得中のことをプレゼンテーションさせるように促し、企業に対しては、社員がプレゼンテーションを行う素地を整えることが大切であることを伝えています。
プレゼンテーションとは、具体的にどのようなことをすればよいのでしょうか。
どのような場合に育休取得により社員間で軋轢が生まれるかというと、社員が理由もなく単に制度があるから育休を取得するという場合です。きちんと、育休を取得しなければならない理由をプレゼンテーションした上で育休を取得すれば、企業や他の社員も納得しやすくなります。
例えば、産後1か月が会社の繁忙期だったとします。産後1か月はパートナーにとって一番大変な時期であり、パートナーのケアのために育休を取得したいという主張や、産後1か月はパートナーの実家の親が赤ちゃんの面倒を見てくれているので仕事にコミットするが、代わりに繁忙期を過ぎた後にはパートナーにキャッチアップするために育休を取得したいという主張を社員が行えば、企業や他の社員としても納得しやすいと考えます。
育児休業を取得することは権利行使ですが、これに伴いある程度のことをやるべき義務が社員には課されていると思います。社員が育休を取らなければいけない事情をきちんと説明すれば、企業としても譲歩できない事項や譲歩できる事項を提示することができ、社員との調整を図ることができます。これが育児休業制度の本来のあるべき姿のはずです。
企業を転職する人が多い世の中で、企業に対するロイヤリティーを上げて、視野を広げた人が企業に居続けるというのは、長い目で見て企業にとっていいことですよとか、また、そういう制度がある会社自体、若い男性女性が就職したくなる企業だからより優秀な人を採れるんですよとか、そのようなことを経営者におっしゃるということですか。
まさにそうです。長く育休を取れる企業を目指したいのか、育休後に長く働いてもらえる企業を目指したいのかどちらですかということを言うと、大体後者です。ただ、制度上は前者を作ろうとしていますが、そもそもそれは正しくないのではと考えています。
1年育休を取って戻ってきて、復帰後に育児ができないので辞めましたという社員はいます。企業からするとこれは最悪だと思います。ここにはキャリアの話も絡んできますが、本人にとっても企業的にも、キャリア的には長く休むということはネガティブだと思います。それならば、育児休業から早く戻ってくることができる、すなわち育児と働くことを両立できる企業を作りましょうと経営者に説明をしています。これは女性のキャリア構築にもつながる話にもなります。
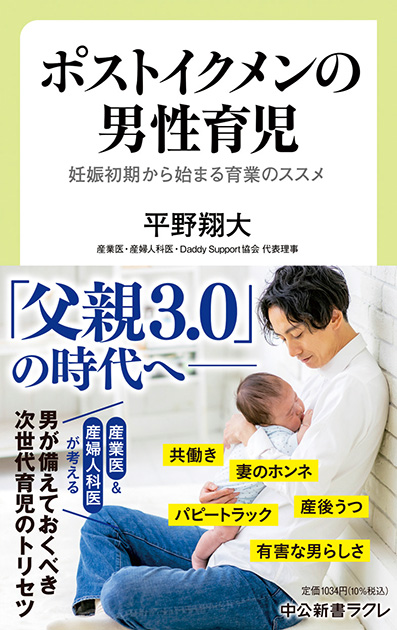
これからの将来像について
平野先生のこれからの将来像をお聞きしたいのですが、男性の育休が浸透してきた後、どのようなご活動を考えておられますか。
私は、どちらかというとパッシブ(受動的)な人間です。そもそも育児休業の問題に取り組んでいる理由についても、私は未婚で子どもがいるわけではないため、自身が困っているからというわけではなく、社会に課題があり、そこに自分の専門分野によって寄与できるならばやってみようというスタンスで始めています。様々な話題に関して当事者ではないことはとても大事だと思っており、強い思いがないがゆえにある意味客観的に物事を見ることができています。
そのため、今後も、5年後や10年後などそのときに世の中に存在する課題に、自分の専門性を使い取り組んでいきたいと考えています。

弁護士が果たすべき役割
最後に、弁護士の役割について、育児などの領域に関して外部の専門家としてお手伝いできることはありますか。
世の中に潜在化している雇用トラブルはまだまだ多くあると思います。マタハラ・パタハラが行われていたとしても、それがハラスメントと認識していない方も多いです。都心の大企業ではこれらのハラスメントはなくなってきていますが、中小企業ではまだまだハラスメントが横行していると思います。このような潜在的なトラブルがもう少し掘り起こされていけば、企業側としても動かざるを得なくなってくるのではと考えています。
企業もしくは労働者から相談を受けるときも、当事者が言わなくとも、実は育児の問題が背景にないですか、介護の問題が背景にあるんじゃないですかということを我々弁護士から質問したほうがよいのではないでしょうか。
そのとおりだと思います。これは産業医もできていません。メンタル不調を見たときに、背景の育児とか介護の問題を正視できている産業医は決して多くないです。
男性のメンタル不調でなぜか若い人が多いですと言う方に、育児のことを聞いてみたらどうですかと伝えたところ、本当に育児の事例がたくさん出たという会社がありました。男性たちは、会社に対して自分の育児のプライベートのことは言っちゃいけないと思っていますが、メンタル不調の背景には育児問題が意外とあります。人のキャパシティーは一つなので、どっちかがあふれるとどっちかもあふれてしまいます。そのような関係性を本人も理解しておらず、会社も把握できていなかったため、気がついたら本人が病んでしまい辞めていったという事例がすごく多いです。
本日は示唆に富むお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
2025年(令和7年)3月6日(木)インタビュアー:飯島 奈絵
折田 啓
玉巻みちる
豊島 健司
松村 隆志
吉村まどか