弁護士会から
広報誌
オピニオンスライス 1月号
-
慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科 教授
南澤孝太さん
本年度大阪弁護士会は、「Equity(エクイティ)の実現~真に公正・公平な社会を目指して~」をスローガンにしています。生来の能力や環境に拘束されることなく、誰もが潜在力を発揮できる社会を目指したいという心意気が込められているのですが、最先端のテクノロジーを駆使して、一足早くエクイティを実現されている方がいました。今回インタビューした南澤孝太さんは、サイバネティック・アバターや触覚技術、ロボット技術の専門家であるほか、「OriHime」というアバターロボットを用いた「分身ロボットカフェ」と協働し、様々な事情を有する人に自己実現の場を提供されています。
-

アバターとはどのようなものか、またサイバネティック・アバターの研究をされるに至ったきっかけについて教えてください。
アバターとは、自分の存在をインターネット越しに別の場所にテレポーテーションできる技術です。研究業界では「Telexistence(テレイグジスタンス)」あるいは「Telepresence(テレプレゼンス)」とも呼ばれ、1980年代から研究が始まりました。
Telexistenceとは「遠隔(tele)」と「存在(existence)」を組み合わせた造語、つまり人の存在そのものを離れた場所に届けるということです。現在では、障害のある方や様々な理由で外に出かけられない方が「OriHime」に代表されるアバターロボットを操作して、
自宅や病院から働きに行ったり旅行に出かけたりすることができるようになりました。
僕は学部や大学院の頃にバーチャルリアリティーの研究室に所属していて、そこから現在の研究が始まりました。例えばゲームの世界もそうですが、ゲームの中のキャラクターになりきって、そのゲームの世界の中で活躍する。ゲームやバーチャルの世界の中では空も飛べるし、敵と戦うこともできるし、現実ではできないような自分になれる。それがリアルの世界でも起きたら、どういうふうに自分の新しい可能性を引き出せるかというのが、サイバネティック・アバターの一番基本的な哲学です。
僕はずっと身体の感覚を扱っていて、人が身体を通じて感じる感覚や、それに応じて行う運動を、デジタル技術を通じて記録・共有したり拡張したりする、このような技術を「身体性メディア」と名付け研究しています。人は自分の身体を使って移動し、身体を使って実際に物をつくったり仕事をするわけですが、書類のDXや業務のDXなど今までは手書きだったものがデジタル情報になっているのと同じように、デジタルな身体だったりデジタル技術を介してつながったロボットの身体で行動できるようになれば、自分が今いる場所じゃないところで働いたり、それこそ自分をコピーして3人の自分でいろんなことをすることもできるのです。これを「身体性のDX(デジタルトランスフォーメーション)」と呼んでいます。
遠隔でアバターを動かすだけでなく、感覚もコピーするということでしょうか。
僕らが研究を行う中で大事にしているのが、人の感覚の部分です。例えば物を見る、耳で聞いて人と話すだけじゃなくて、何かの匂いを感じるとか物に触れた感覚、どういうふうに自分が力を入れて身体を動かして物に触れるかという触覚というのがすごく大事で、例えば今レコーダーで僕の声を記録しているように、触覚を記録して、それを後で再生できるようにするということをやっています。 「テクタイルツールキット」という装置を2010年につくって、触覚の記録・再生が誰でもできるようになりました。触覚だけではなくて、人の技だったり、スポーツのアスリートの身体の感覚だったり、全身の運動というのがデジタルに乗ってくるともっと新しい可能性が生まれるよねということで、もともと「Haptic Media」(触覚メディア)と呼んでたんですが、今はもう少し広げて「Embodied Media」(身体性メディア)と呼んでいて、これを研究室のテーマとして活動しています。 人が感じる触り心地を記録して遠隔地にいる人に伝える技術をつくっていますが、それを応用して、例えばゲームメーカーさんと一緒に、全身で触覚を感じられるスーツを開発してゲームの世界を全身で体感しながらプレイできるようにしたり、自動車メーカーさんと運転体験を触覚刺激で拡張したり、化粧品メーカーさんと肌の触り心地を計測して可視化したり、ということをやっています。そんな最中に、コロナ禍が来て、人と触れ合えない世界が来ました。僕らの研究室でも、そもそも触れられないからということで様々な共同研究が頓挫しましたが、日本以上に欧米で社会課題になっていたのがスキンハンガー―皮膚が飢える、ハングリーになるという心理的ストレス状態です。 欧米では握手したり抱き合ったり、日常生活の中に身体接触が自然に存在していて、接触を通じて他人との信頼関係を築いていたのに、それが全部なくなって、相手とのつながりが分断される状況になって、もしかすると今のアメリカやイギリスの分断はそれも1つの理由になっているかもしれないですが、そういった人と人とのつながりにおける触覚の役割というものを改めて見直す期間だったと思います。 コロナ禍を経て、オンラインでの人々の会話や会議が日常になりました。今、僕らは、オンラインのコミュニケーションでも、お互いがちゃんとつながることができる、例えば携帯電話で声が届くように、オンラインでお互いが触れ合える、そんな世界を実現しようとしています。2022年からNTTドコモさんと一緒に取り組んでいる「フィールテック」というプロジェクトでは、6Gネットワークの時代に向けて、お互い会話をするだけではなく、触れ合えるようなメディア環境の実現に向けて研究開発を行っています。

そのように以前では考えられなかった技術が出現すると、社会もそれに合わせて変わっていく必要がありますよね。
そうですね。僕が現在所属しているメディアデザイン研究科(KMD)は、慶應義塾の中でも比較的新しい大学院で、「学際的」という概念を超えて多様な人々が集う面白い組織でして、 デザインとテクノロジーとマネジメントとポリシーの4つの柱を持っています。デザインは新たなプロダクトや体験、ライフスタイルなどをつくる領域。 テクノロジーはまさにAI、ロボットなどの技術の領域です。マネジメントというのは、実際それを事業化してビジネスを興していく領域。 大企業と一緒にやったり、スタートアップを起業したりして、実際にビジネスにしていく。ポリシーというのは、まさに弁護士会的なところかもしれませんが、ポリシー・メイキングをする領域です。 例えば触覚を記録して伝えられる世界が来たときに、そこにはその人の技とかも含まれているかもしれない。職人さんやアスリートの手の感覚の情報は技そのものですよね。それって知財なんじゃないか。 今まではデータになっていなかったものがデータにすることができるようになったときに、もちろんいい側面、悪い側面があって、いい側面は、それをいっぱい集めれば人間国宝AIをつくれます。 それでロボットを動かせば、ロボットが人間国宝の技をコピーすることができるようになります。一方で、技能が流出したり勝手に使われてしまうリスクも存在します。 共同で研究プロジェクトを行っているオリィ研究所さんが取り組んでいる「分身ロボットカフェ」には寝たきりの方もいるし、腕が上がらない方もいるし、車椅子の方もいますが、 例えばちょっと指を動かすだけでアバターロボットを自在に動かせるような技術ができれば、障害を持っている方もみんなと一緒に働くことができます。 だけど、そのときも彼らの肉体は介護が要ります。旧来のルールでは、24時間介護が必要な方がアバターを使って働くと、働けるなら介護は要らないだろうとなってその時間は介護支援を打ち切られてしまう。 それで何が起こるかというと、1,200円の時給を稼ぐために、1時間5,000円とかそれ以上かかる介護費用の補助が受けられなくなる。これは実はこんな最先端技術を使わなくても起きていて、 コロナ禍で車椅子の方でもリモートワークで他の人と対等に働けるようになったときにも、介護保険が適用除外になるという問題があったり、ただ、これはコロナ禍で課題が顕在化したので、 今は各自治体でリモートワーク中の介護支援を行うという特例をつくれば、それが通常のリモートワークでもアバターロボットでも、介護保険の適用対象になるんです。 ただ、日本全国に4,000以上の自治体がある中で、条例をつくる対応ができている自治体はまだ数百です。ですから、住む地域によってはリモートワーク中も介護支援を受けられるけれども、 多くの自治体ではまだ難しい、という格差が生まれてしまっている状況があります。

国が法律で定めるべきということでしょうか。
そうなんです。自治体にとっては個別に条例を制定する手間もあり予算措置の問題もあり、本当は自治体じゃなくて国レベルでやるべきという話は僕らもしています。今は新しい技術でどんどん世の中が変わっているので、ポリシー・メイキングも含めてやらないといけないと思います。
あと、当然犯罪みたいなことも起き得るわけじゃないですか。例えばロボットを海外から操作して爆弾を仕掛けるとか人を傷つけるということもできちゃうわけです。Zoomのようなオンライン会議システムで海外から誰か入ってもせいぜいできるのは詐欺ぐらいで、
それは電話と大きく変わらないというレベルの話なので今までの法律で扱えていたけれども、それが身体をもって動き回って、あるいは海外からドローンで入って何かを仕掛けるとかできてしまう、ということが既に現実になりつつあるときに、
これは入国に該当するんじゃないのか、という疑問も生じるわけです。肉体は国外にいながら、アバターロボットで観光したり人に会ったりできるついでに犯罪を行うこともできるかもしれないということが起きている今、
そろそろ法律とか社会制度設計の側も、何か起きてからではなく、今こういう技術が開発されているから事前に備えていく、というふうに、ポリシー・メイキングも一緒にやらなきゃいけない。ポリシー・バイ・デザインという考え方があると思いますが、
先端技術と社会との距離が近づいている今、技術と制度が一緒に動く必要がある、ということで、KMDでは2008年に研究科が生まれた段階で、ポリシー(政策)を1つの柱として入れています。未来の社会をつくるということは、単に物をつくるだけじゃなくて、
ビジネスをつくることでもあるし、制度をつくることでもあるという考え方でやっています。
分身ロボットカフェについて、具体的な内容を教えてください。
分身ロボットカフェは、吉藤オリィさんという社会起業家が2018年から提唱してきたプロジェクトで、障害をもっていたり何らかの理由で外出困難な人々が、アバターロボットOriHimeを自宅や病院から操作することで、 カフェの店員として働くことをきっかけに、社会や人との接点を取り戻していくというコンセプトです。オリィさんは、自分自身も身体が弱くて不登校だったこともある経験から、 「ベッドの上から社会に参加できる」という理念で、オリィ研究所というスタートアップを立ち上げて取り組んでいたんですが、この活動をもっと技術的にも進化させ、 実際に社会の中に根差したものにしていこうというタイミングで、2020年に内閣府のムーンショットという研究開発事業が始まり、ぜひ一緒にやりましょうということでお誘いして、 他にも多彩な研究者を巻き込み、Project Cybernetic beingが立ち上がりました。オリィさんたちもこれをきっかけに2021年6月に東京の日本橋に分身ロボットカフェの常設店舗を立ち上げました。 OriHimeを操作して働いている人はパイロットと呼ばれているのですが、パイロットには、生まれつき重度の障害を持っている方から、身体には障害はないけれども心理的な要因で人と対面で話すのが難しかったり、 家族の介護等で外出できないという方などいろいろな方がいらっしゃいますが、そういった方々が日々生き生きとお客様をおもてなししています。
そういった方もロボットを介したら他人と接することができるのですか。
それがすごく面白いところで、物理的な障害や恐怖がないというのが大きいと思います。障害の当事者にとっては実際に移動しようとすると体力的にも費用的にも時間的にも、周りの人を巻き込まざるを得ないという点で心理的にも大変だけれども、 アバターロボットだと完全なバリアフリーになるんですね。パイロットの一人に、マサさんという人がいるのですが、彼は手を動かせなくても、視線入力でOriHimeを操作できます。 マサさんは4~5年これを続けているということもあって、多分脳も進化しているんだと思いますが、目がものすごく細かく器用に動くんです。しかも、最初の1年は目の筋肉がつったりしたけれども、 慣れた今では全く疲れないみたいです。OriHimeロボット越しに、目を合わせて会話したり手を振ったりするんですが、それも彼が視線入力で操作しているんです。 車椅子の方とかいろんな方がアバターロボットという、自分と異なる身体を自然に使って日々働いています。マサさんは器用なので複数のロボットを同時に動かすこともできて、 1つのOriHimeでお客さんとお話しながら、「コーヒー持ってきますね」と言って別のOriHimeを操作してコーヒーを持ってくるんですよ。


テーブルにいるロボットと動いて何かを持ってくるロボットがいるのですか。
ふだんはそれぞれ別の人が操作するんです。ムーンショット研究プロジェクトの実証実験として行った「複数アバター分身実験」では、マサさんが5体のOriHimeを全部1人で操作していて、 店の入口のOriHimeで「いらっしゃいませ」と言っていたのもマサさんですし、テーブルのOriHimeに先回りして「こちらです」と言って、「注文どうぞ」「じゃあ、持ってきますね」と言ってさらに別のOriHimeで持ってくる 。 身体性のデジタルトランスフォーメーションというのはまさにここで、自分が操れる身体がいろんなところにいくつもあれば、こっち行ってあっち行ってとできます。自分で歩かなくていい。 そうすると空間の制約とか身体の制約を全部超えていくことができます。今パイロットたちは、東京のカフェで勤務した後「次は大阪に行ってきます」と、3秒後には万博会場のカフェのシフトに入ったり、 そのまま次はデンマークの海外店舗のヘルプに行ったりと、まさに国境を超えて活躍しています。
障害を乗り越えてというレベルではないですよね
オリィさんがよく言ってますが、彼らは人生の先輩だと。つまり、我々もいつ足が動かなくなって車椅子になるかも分からないし、いつ病気になるかも分からないし、寝たきりになったとしても、自分がアクティブに活動したければ彼らを見れば学べるということです。 もちろん彼らは肉体に制約があるからこそこういうのを使わざるを得ないというのもあるんですが、パイロットによっては扶養を外れちゃうくらい働いて自立して一人暮らしを始めた方もいます。皆さん最近は、寝たきりなのにちょっと忙し過ぎると笑ってます。
先生の研究を見ていると、SFの世界が現実になっているような気がします。
SFが本当にリアルになってきていると思います。攻殻機動隊などはこの分野の研究者のバイブルですが、星新一のショートショートも今読むとかなりリアリティがあって、「声の網」という短編があるのですが、これは現在のインターネットでとっくに実現されています。 小説ではまだ電話がモチーフで、電話で何か言うとそれが届くとか、電話で何か言うとそれが現実になるみたいな話です。今はネット販売でポチッとすると最速1時間後には届くじゃないですか。「肩の上の秘書」はセールスマンがオウム型のAIロボット越しに会話する物語ですが、まさに今我々がChatGPTなどの生成AIでメールを書いている状況を彷彿とさせます。 OriHimeは手軽に使えるかわいいロボットとしてデザインされていますが、研究プロジェクトの中では、もっと身体性能の高いロボットもつくっています。最近取り組んでいるものの1つは野球ロボットで、バットを持って打つアバターロボットなのですが、AIによる行動アシストが入ることで、自分が生身では打てない球も打てるようになり、身体能力を拡張することができます。

AIだけで、人間性みたいなものがなくなってしまった社会でいいのかと思うのですが、今の世の中の動きを見ると、我々は刺激を受けるだけの客体になっていて、映像を見せられて、アウトプットもChatGPTがやったらどこに人間性があるのかという話になってくると思います。先生が触覚の研究をされる上でAIとの関係性を教えていただけますか。
まさに今その流れだと思いますが、技術的には職人さんの高度な身体知も全部AIに組み入れるという可能性まで含めた研究をしています。
ただ、それで人間の様々な知というものを吸い上げるだけだと誰も幸せにならない。僕らがもともと触覚や触れ合いを研究しているのは、最終的に、人のQoL(Quality of Life・生活の質)を上げるためにこういった技術を使いたいからです。
僕も小学生のときから眼鏡をかけていますが、眼鏡がなかったら周りのものが見えないまま生活を送らなきゃいけない。そうすると、仕事の幅も遊びの幅も狭まるけれども、眼鏡があることによってそれが広がるわけです。
そういった眼鏡みたいに人の人生の可能性を広げるような技術をつくろうと。だからこそ、先ほどの分身ロボットカフェのように、障害によって可能性を閉ざされている人が、新しい身体を手に入れることで可能性が広がるといった未来を実現しようとしています。
職人さんの技をデジタル記録するというのも、2024年、沖縄の陶芸家さんのところに毎月のように伺って、20年、30年と職人をやっているような人たちの技や感覚を記録していました。
この映像は、若手の職人が目の前でベテラン職人の陶芸仕事を見ながらその感覚を感じているところです。ここでつくっている壺は結構難しくて若手の人にはつくれないんですが、リアルタイムにベテラン職人の感覚を感じながら、「ここは意外と力を入れないんですね」と言ってて、「おまえ、いつも言ってるだろう」と突っ込まれています。
それで初めて分かると。力を入れないという言葉だけでは分からないんですね。
言葉だと伝わってないんですね。こことここに力を入れて、こっちは抜くんだということが分かるとコツみたいなものが分かるんです。こうしてデータをいっぱい取るとAIができるので、職人さんの技がインストールされたロボットもつくることができます。 そのロボットをほかの人が操作すると、自分では本来まだできないはずの力加減をロボットが修正してくれるので意外と高度な技能が必要なものでもつくれちゃうようになります。いわば、二人羽織状態ですね。 手取り足取り後ろから教えるみたいなことをロボット越しにやると誰でもどこでも技を身につけることができるようになる可能性があります。
技術の伝承が途絶えがちになるところをこういう技術で残していくということでしょうか。
はい。彼らと最初に話したときに、伝統を大切にする現場にロボットやAIを持ち込むのは、ちょっと嫌がられるかなと僕らも思ったんですが、逆にすごく面白がってくれて、「AIとか最近ニュースに出てくるけど、私たちも関係あるんだね」と。 「AIに食われるんじゃなくて、自分たちがうまくAIを使いこなしていきたい」と言っていただいて、この共創がスタートしました。彼らが今やりたいと言ってるのは、やっぱりこういった作品はちょっとお値段が張るものなので、 海外の人にいかに買ってもらえるかが勝負で、海外のお店で職人の熟練の技を体験してもらうことができたら、値段に対する理由づけになる。この技がこの作品を生み出しているという背景が伝われば商品の価値につながるから、例えば数万円する器であっても買ってもらえる動機づけになるんじゃないかという話もしています。
疑似体験で付加価値をつけるわけですね。
まさにそうです。だけど、技能をAI化して誰か別の人がそれを活用して勝手にどんどん使えるようになってしまうと、職人の価値が失われディストピアになるので、ここを法律的にどうするのか、制度的にどうするのかが大切です。
どこまでをその人の著作権的なものだと認めるか。インターネット上で、自分のデータの行き先をトレースできるか。最近だとNFTとかブロックチェーンとかがありますが、自分の技がどこに伝播していって、別の会社がそれを使って稼いだときにちゃんと利益が還元されるならありかもしれないけれども、でも、
その仕組みはまだ全然ない状態です。技術を活用するということと、流出や悪用を防ぐということを両方並行してやらなきゃいけないと思います。それがもうSFで描かれる空想の未来じゃなくなっているという話です。いまアメリカや中国は資本も人も集中的に投入していて、
とにかく人間をたくさん雇ってまずは単純作業をどんどんAIに学習させて、それを工場に使うなり軍事に使うというのを繰り返し試していくという方向に行っているので、日本もこの流れに乗らないとどんどん差が開いてしまうので、政府としてもようやくAIロボットの基盤づくりを始めようとしています。
一方で、障害がある人がこういったロボットを使って活躍するときに、働いたら介護保険を切るぞと言われるようでは困るので、肉体はサポートが必要だけれども、ロボットを使えば働けるよとか観光に行けるよというときにちゃんと後押しできるような制度設計が肝要ですし、
そこで得た稼ぎがちゃんとその人に行くようにする必要があります。例えば人間国宝の人が自分のデータを提供しますとなったときに、最終的にちゃんとその人の収入につながらないと、ただAIに長年の努力を吸われて終わるので、そこら辺の仕組みをどうするのかというのは、
まだ技術が先行しているところで、僕らも議論はするし、法律的な専門家の人たちと議論をする機会は増えていますが、次はそれを法律とか制度、ルールとして整備していかなきゃいけないです。
多くの場合、実際に事例が生じてからじゃないと法律は整備されないじゃないですか。でも、事例ができるということは何かトラブルが起きている状態ですよね。今は技術の進展が早いので、事例ができるのを待っているともう手遅れになってしまいます。
ロボットも急速に普及し始めて既にトラブルが起きているところもあると思いますし、Zoomで会話している相手がCGでつくられたフェイクの人格だったということも既に起きています。今は既存の法律を解釈して対応しているとは思いますが、
だんだん解釈にも限度が訪れると思います。ロボットがどこにでもあるという時代が来て、それが何か事故を起こしたときに、それはロボットのメーカーの責任なのか、それとも操作していた人の責任なのか。でも、本人が海外から入っている場合、
それはどちらの国の法律でさばくのかなど、今まであまり想定されていなかった前提が生まれつつあるからこそ、なかなか難しいですし、面白い点でもあります。
10年ほど前に1度、裁判所の司法研修で呼ばれたことがあります。当時、AIやVRも今ほど普及していなかったですが、3Dプリンタによる銃器製造など、テクノロジーの社会的影響が話題になっていた時期でもあり、遠隔で相手に触ることや、
職人の技術をデータ化するみたいなものが、いずれ裁判ざたになるでしょうから、と言われました。先端技術を世の中に広がる前に捉え、先回りして対応を考えておくことが今後ますます必要になっていくのではないかと思います。
大阪万博にも出展されていますね。
万博でもいくつかのプロジェクトを出展していますが、その1つに、ALSという身体が動かなくなる病気をもった方の身体を拡張するということを行っています。武藤さんは12年前にALSを発症し、現在は自分で身体を動かすことも声を出すこともできませんが、目は動くので、
視線入力でタブレットを操作して、声を失う前に記録しておいた自分の音声を使って、デジタルボイスで会話をするということを日常的に行われています。ムーンショット研究の一環として、ロボットアームによって、彼の車椅子に装着する腕をつくって、
これを脳波(BMI: BrAIn Machine Interface)を使って操作できるようにする BrAIn Body Jockey プロジェクトに取り組んでいます。
万博では武藤さんが視線入力でDJをしたり、脳波で操作するこの「新たな腕」を使って車椅子ダンサーの かんばらけんた さんと一緒に踊るといったライブパフォーマンスを行いました。
武藤さんがBMIで操作するロボットのアームでみんなを盛り上げると、お客さんも一緒に拍手をしてくれて、ちゃんと気持ちが伝わり合う場が成立しました。ALSは筋肉は動かないけど皮膚感覚は正常だし、
聞くとか認知する方は完全に正常なんです。なのに身体が動かないからつらいんです。ロボットアームで握手会も行ったんですが、お客さんと握手をするとロボットの指先のセンサーを通じて、ご本人も腕に握られた感じを感じられるようにして、
そうすると本人の中ではちゃんと触れ合っている感覚が生まれたと言っていただけました。
衣装デザイナーさんも面白がってくれて、特別な服をつくってくれました。動かない肉体の2本の手と、動くロボットの2本の手で合計4本の腕を通せて、でもすごく自然に見える。眼鏡と一緒で、ファッションの力が加わることで、単なる道具ではなく、もう彼の身体の一部になるのです。
以前の先生の記事で、AI等々が発展していったときに、2040年ぐらいに人間は自分たちは何のために生きているのかということを疑問に思い始めて、2050年あたりには、自分のバーチャルな身体で時間や空間を飛び越えていくんじゃないかというのを拝見しました。そのあたりの未来像はどのように見ておられますか。
この話は、ムーンショット研究を企画した2020年に描いていたストーリーなのですが、最近、それはのんびり考え過ぎたなと思っています。2025年の現在、既に我々は、ChatGPTをはじめとする生成AIの進化を眼の前に、何のためにこの仕事をしているんだっけと、思い始めています。例えば判例調査もChatGPTの方が早くない?
となってるんじゃないでしょうか。僕らの研究の現場でも、既に人が頑張って調査したレポートより、ChatGPTに聞いた方が早いし正確なんですよ。だから、2040年ではなくて、もう今既に起きている話かもしれなくて、思ったより早かったという実感です。ロボットに人のスキルがコピーされていくことも、もう防げなくて、
世界中で既定路線として進みます。というのは、少子高齢化による人手不足を考えるとやらざるを得ないし、やる方が正しい世界になっているけれども、そのときに人間って要らなくない?とならないようにすることが本当に大切です。2030年頃には様々な現場で、人間が働く意味や自分で何かをする意義というものが揺らいでいくだろうというときに、
一方で、分身ロボットカフェの方がすごく生き生き働いているのを見ると、あそこに正解があるんじゃないかと思います。
AIやテクノロジーで自分の不便を解消するとか人手不足を解消することはもちろんやるべきだけれども、やりたいことや自分の向かいたい方向性、あるいは、自分は今までこういう人生を歩んできたけれども、こっちでもよかったんじゃないかという別のルートに切り替われる。
先ほどの技の伝承の話もその1つだと思っていて、例えば昔は寿司職人になりたいと思っても修業に何年かかるのかという世界でしたが、いまは脱サラして数週間で学んで海外で稼ぐという事例も増えている。可能性は広がっていて、技能を人と人との間で伝えられるようになると人の選択肢が増えるはずだと思います。
今の仕事が続くかどうか分かりませんし、AIに奪われるかもしれないけれども、そのときにこっちの道に行きたいというときに行けるとか、それを自分で選択して選ぶところの障壁が下がる。これは、先ほどの寝たきりだから自分はもう働けないし、学校にも行けないよねというところから、学校に行く、働くという選択肢が生まれるというのと同じことかなと思います。
そういったことが、以前は2040年に実現し、2050年までに普及すると言っていたけど、今の技術の進化の速さを見るに、全部10年前倒しになってくるかなという気がします。

若い法律家に、今後の技術発展の中で、どういうことを心がけていったらいいのかというアドバイスをいただけますか。
想像力というのが今すごく大事な時代になっているように思います。何か起きてからそれに対処するのではもう遅くて、今のこの時代の流れやその先の未来にこんなことが起こり得る、こんなことが可能になるけれども、その可能になるということには表と裏が絶対にあるので、
こんなことができるようになるという一方で、こんな事件やこんな悪さが起きるなど、この想像を常に更新して、未来に備えていくということが大事だと思います。僕らみたいな、テクノロジーをつくっている人間は、ある意味「少し先の未来」をつくることを仕事としているので、
僕らと法律家、特に若手の法律家の方々がうまく一緒に動くことができれば、少し先に起こり得るかもしれない未来に対して事前に備えておくことができる。これがすごく大事だなと最近思っています。既にそういうことに興味を持って僕らと一緒に動き始めてくださっている方もいますが、
そういう動きがもっといろんな領域で起きていかないと、これから先の未来を良くしていくことは難しい。10年前、20年前と今では時代が変わってしまって、何か起きてから対処すれば間に合うだろうという世界ではなくなったというところで、想像力を持って少し未来に備えていくという動き方が大事だし、
それを僕らも一緒にやりたいなと思っています。
先ほどの分身ロボットカフェをはじめ、研究の現場で実現されつつあるものを、うまく社会の中にインストールして、制度をつくっていければ、ちゃんと社会が良くなる方向にもっていけると思います。未来づくりというのは技術だけでは駄目で、それが社会に実装されるプロセスに法律や制度というものがあるので、
そこを敢えて前倒しで積極的にやっていく。事件の処理をするだけではなくて、新しい未来のための法律デザイン、制度のデザインみたいなことができてくるとすごくいいし、今こそそれが求められている時代に来ていると思います。
最近は、法学の分野の若手の研究者や実務家の方もこういうところに興味を持って一緒に活動してくれることが増えてきました。その要因として、みんなの肌感として、社会が変わる時間軸が全く変わったというのがあると思います。僕らの師匠の70代の世代の人たちは、30代の頃に新しい概念を発明したら、
30年のキャリアを通してそれを実現し、引退する頃に社会に送り出せればまあ満足して一仕事終えられる、みたいな世界だったかと思うんですが、今は、僕らが何か発明すると、5年くらいでもうそれがいくつかの場所で使われ始め、
10年後には製品に入って普及している、くらいの時間感覚になっています。だからこそ、僕たちはつくって終わりじゃ済まなくて、社会に入るところまで見届けるという責任が生まれている。社会科学や法律の側も、判例が集まってからそれを分析して法律を変えていると、
法律が変わった頃には既にその技術とか社会の状況は過去のものになっていて、周回遅れじゃ済まないぐらいの圧倒的な遅さになってしまう。ですから、少し先を予測してそこに備えて、何かが起こる頃には法律や制度設計が何とか間に合っているという動きに変えていかなきゃいけない。
過去の分析では追いつかないところは、少し未来に対するアプローチが必要だよねというのは研究者共通の危機感として生まれています。これは法曹の現場でも似たような状況なのではないかと思うので、ぜひ、僕らのような技術をつくっている側と一緒に手を組んで考えていただければと思います。

本日は刺激的なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
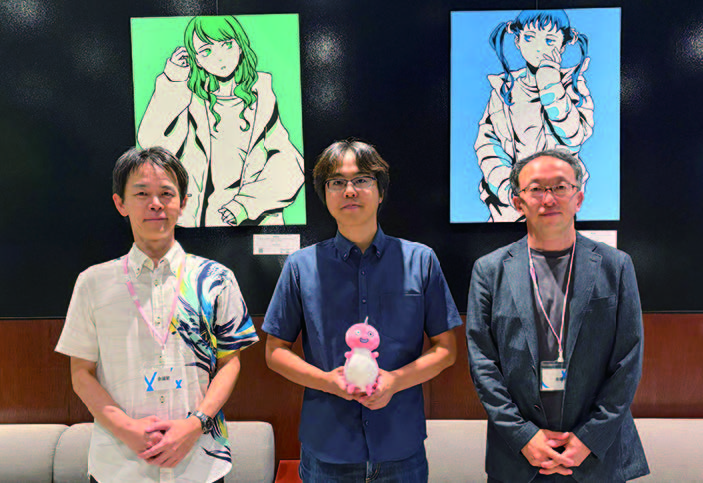
インタビュアー:和田義之
廣政純一郎